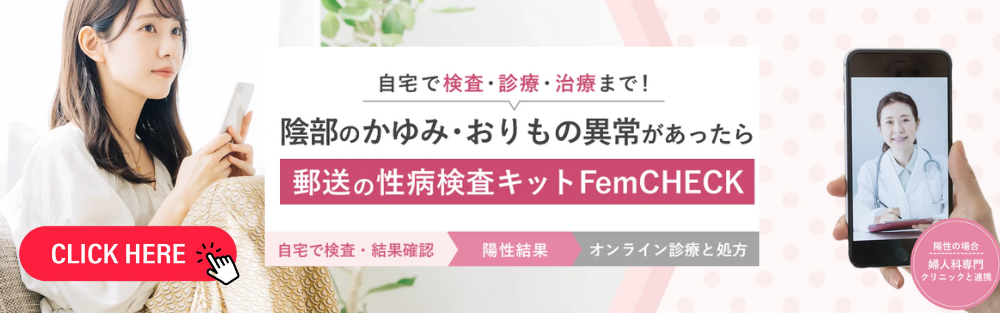約3人に1人が35歳以上での出産となる昨今、母体の採血で行える検査方法が普及し、多くの妊婦さんが何らかの出生前検査を受けています。
出生前診断導入の趣旨は、命の選別ではなく「出生後のケアや支援を事前に理解し、対応策を検討すること」とされています。
「念のため」「安心したい」という気持ちで受けた検査結果が陽性だったとき、大きなショックを受けるでしょう。
この記事では、出生前診断で陽性が出た場合の中絶の可能性や法的根拠、中絶が認められるケースについて詳しく解説しています。
陽性の結果を受けてお悩みの方はもちろん、出生前検査を受けるかどうか迷っている方もご一読いただき、話し合いや相談の参考にしていただければ幸いです。
参考元:厚生労働省|第2回NIPT等の出生前検査に関する専門委員会2020年|女性から見た出生前検査
出生前診断で陽性の場合、中絶を認められることがある

日本では、出生前診断で胎児の異常が判明した場合でも、胎児の異常を理由に中絶が認められるわけではありません。
母体保護法では、中絶が認められるのは以下の2つの場合のみです。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
母体保護法(昭和23年07月13日法律第156号)第14条
(妊娠を続けることや出産をすることが、身体的な理由や経済的な理由により、妊婦の健康を大きく損なう恐れがある場合)
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫かんいんされて妊娠したもの
(暴力や脅しによって、または抵抗したり拒否したりすることができない状況で性行為をされて妊娠した場合)
そのため、胎児の遺伝子異常が発見された場合でも、胎児の異常そのものを理由としているのではなく、あくまで母体保護の観点から中絶が認められるのです。
ただし、中絶はいつでも可能なわけではなく、中絶が可能な時期は制限があります。
人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
母体保護法(昭和23年07月13日法律第156号)第2条
母体保護法第2条で定められている「胎児が母体外において生命を保続することのできない時期」は、「妊娠22週未満(21週6日まで)」とされています。
そのため、中絶を考えている場合は、中絶可能な期間内に出生前診断の結果が得て、意思決定ができるよう、スケジュールを調整する必要があります。
出生前診断後に中絶が認められるケース
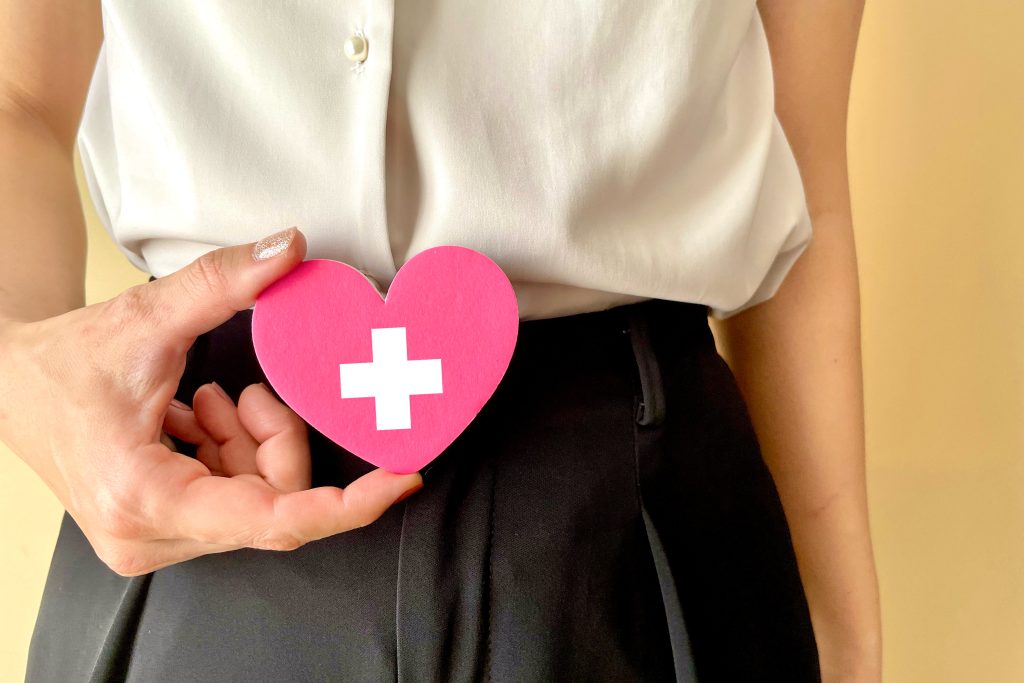
出生前診断で胎児に異常が見つかった場合の中絶について、具体的なケースを見ていきましょう。
妊娠22週未満である
日本では母体保護法により、中絶は妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)に限って認められています。
なぜ妊娠22週未満なのかというと、現在の医学では、妊娠22週頃から胎児が母体外でも生存できる可能性が出てくるとされているためです。
妊娠22週を超えると、中絶ではなく「早産」となり、生まれた赤ちゃんは「人」として扱われるため、中絶は認められないのです。
出生前診断の結果がわかる時期は検査の種類によって異なりますが、特に確定診断となる羊水検査は15週以降でないと実施できず、結果が出るまでに2〜3週間かかることがあります。
妊娠18週~20週頃には多くの妊婦さんが胎動を感じる時期になっており、中絶の決断に時間がかかる場合も多く見受けられます。
出生前検査を受けるか悩んでいる場合でも「検査結果が出るまでの期間」や「中絶の準備にかかる期間」など、時間的な制約を医師に確認しておくと、後悔しない選択へとつながるでしょう。
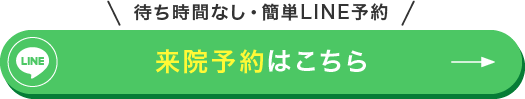
胎児の遺伝子異常が発覚した場合
胎児に異常が見つかった場合、異常自体が中絶の理由とはならないものの、子育てによる体力的・経済的・精神的負担が母体の健康に重大な影響を及ぼすと医師が判断すれば、出生前診断後に中絶が可能です。
遺伝子異常は、出生後に重篤な障害や短命につながる疾患や、出生後に長期的な医療ケアや特別な支援が必要となる疾患があります。
障がいや疾患を持つ子どもを育てるための支援が地域によって異なる中で、中絶を含む選択肢を検討するために出生前診断を希望される方も多くいらっしゃいます。
出生前診断を希望する妊婦さん、ご家族に対して、医学的・心理的な支援を提供する「遺伝カウンセリング」を行っている医療機関もありますので、主治医や医療スタッフに確認してみると良いでしょう。
胎児異常による心理的ストレス・経済的負担が大きい場合
出生前診断で胎児異常が判明したとき、その子どもを育てることによる心理的・経済的負担が母体の健康に著しく影響すると医師が判断した場合に、中絶が可能となります。
具体的には、以下のような要因が考えられます。
- 障害を持つ子どもの養育に伴う長期的な精神的ストレス
- 特別な医療的ケアや教育的支援に必要な経済的負担
- すでに子どもがいる場合の育児・療養負担
- パートナーや家族のサポートの有無
このような複雑な要因が絡むため、同じ診断結果でも家庭の状況や価値観によって異なる選択をすることも多くあります。
医師は妊婦さんやパートナーの思い、状況を考慮した上で判断を行います。
そのため、医師からの検査結果や疾患についての情報提供と、妊婦さんとご家族が素直に思いを話せる相談の機会を持つことが大切です。
「そもそも出生前診断って何?」と考える方もいらっしゃるでしょう。次は、出生前診断の基本的な知識について解説していきます。
出生前診断とは

出生前診断とは、胎児の健康状態や染色体異常、遺伝子疾患などを妊娠中に調べる検査の総称です。
これらの検査は、胎児に異常が見つかった場合の出産準備や支援体制はもちろん、場合によっては妊娠を継続するかどうかの判断材料となります。
特に、ダウン症候群(21トリソミー)などの染色体異常を調べる検査が一般的に知られています。
ダウン症は知的障害や特徴的な顔貌、心疾患などを伴うことがあり、母親の年齢が高いほど発症率が増加することも有名です。
出生前診断にはさまざまな種類があり、検査の時期や精度、リスクが異なります。
大きく分けると「非侵襲的検査」と「侵襲的検査」の2つに分類されます。
- 超音波検査や母体血液を用いた検査など、母体や胎児に直接的な影響を与えずに行う検査
- 流産のリスクが極めて低い
- 確定診断ではなくスクリーニング検査(異常の可能性が高い方をふるい分ける検査)として位置づけられる
- 羊水検査や絨毛検査など、母体腹部や膣内に針を刺して胎児に関連する細胞や体液を採取する検査
- 確定診断となる
- 0.2〜1%程度の流産リスクを伴う
出生前診断で分かる病気
出生前診断では、さまざまな胎児の病気を発見することができます。
染色体異常
| 疾患名 | 原因・特徴 |
|---|---|
| ダウン症候群(21トリソミー) | 通常2本あるべき21番染色体が3本あることで起こる。 知的発達の遅れや特徴的な顔立ちなどがみられる。 |
| エドワーズ症候群(18トリソミー) | 18番染色体が3本あることで起こる。 重い障害があり、多くの赤ちゃんは生後1年以内に亡くなる。 |
| パトー症候群(13トリソミー) | 13番染色体が3本あることで起こる。 脳や他の臓器に重い障害があり、予後は悪い。 |
| ターナー症候群(X染色体の欠失) | 女児のX染色体が1本しかないことで起こる。 低身長や、将来的に不妊になりやすいリスクがある。 |
| クラインフェルター症候群(XXY) | 男児にX染色体が余分にあることで起こる。 不妊や軽度の知的障害がみられることがある。 |
単一遺伝子疾患
| 疾患名 | 原因・特徴 |
|---|---|
| 嚢胞性線維症 | 粘り気のある粘液ができて、肺や消化器官に問題を起こす病気 |
| 鎌状赤血球症 | 赤血球の形が異常になり、酸素の運搬がうまくいかず痛みの発作や貧血を引き起こす遺伝性の病気 |
| 脊髄性筋萎縮症 | 筋肉を動かす神経が徐々に弱くなっていく病気 |
| 血友病 | 血が固まりにくくなり、出血しやすくなる遺伝性の病気 |
| ハンチントン病 | 脳の機能低下が進行し、体が勝手に動く症状や、記憶や判断力の低下などがみられる遺伝性疾患 |
絨毛検査・羊水検査での検査対象となります。
神経管閉鎖障害
| 疾患名 | 原因・特徴 |
|---|---|
| 無脳症 | 脳の大部分が形成されない致命的な先天異常 |
| 二分脊椎 | 背骨の先が正しく閉じておらず脊髄が露出する先天異常 |
構造異常
| 疾患名 | 原因・特徴 |
|---|---|
| 先天性心疾患 | 心臓の構造に異常がある状態 |
| 消化管閉鎖 | 食道や腸の閉鎖や狭くなっている状態 |
| 横隔膜ヘルニア | お腹と胸の境目にある横隔膜が欠損し、腹部臓器が胸に入り込んでしまう状態 |
| 水頭症 | 脳の周りや脊髄の液がうまく循環せず、脳の中に水がたまってしまう状態 |
| 口唇口蓋裂 | 上唇や上あごの形成不全で裂け目がある状態 |
その他の異常
| 疾患名 | 原因・特徴 |
|---|---|
| 先天性代謝異常症 | 体内でアミノ酸や有機酸、糖などの物質の分解や合成がうまくいかない病気 |
| 胎児発育不全 | 胎児の成長が標準より遅れている状態 |
| 羊水過多/過少 | 胎児を包み込む羊水が多すぎたり少なすぎたりする状態で胎児の腎臓や消化管の病気が疑われる |
これらの病気は、種類や程度によって予後や治療法、生活への影響が大きく異なります。
出生前診断で見つかる全ての異常が重篤なものというわけではなく、治療可能なものや、将来的な影響が少ないものもあるのです。
そして、出生前診断で診断できる異常は、疾患・障がいのごく一部であり、発達障害など、診断できないものも数多く存在します。
出生前診断の陰性は対象疾患の可能性が極めて低いことを示すもので、赤ちゃんの健康を保証するものではないことも十分に理解しておきましょう。
出生前診断の検査方法
出生前診断には様々な検査方法があり、検査を行える時期や精度、リスクが異なります。
1.非侵襲的検査(流産リスクがほぼない検査)
| 検査方法 | 妊娠週数 | 検査方法や特徴 |
|---|---|---|
| 超音波検査 | 妊娠初期~出産まで | 超音波で胎児の形態や発育状況、羊水量などを調べる。 |
| NT(Nuchal Translucency)検査 | 妊娠11~13週頃 | 超音波で胎児の首の後ろの透明な部分(NT)の厚さを測定する。 NTが厚いと染色体異常や心臓奇形のリスクが高くなる傾向がある。 |
| 母体血清マーカー検査 | 妊娠15~20週頃 | 母体の血液中のAFP(α-フェトプロテイン)、hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)、エストリオールなどの物質を測定する。 胎児の染色体異常や神経管閉鎖障害のリスクを評価。 |
| NIPT(新型出生前診断) | 妊娠10週以降(推奨:10~16週頃) | 母体の血液中に含まれる胎児由来のDNA断片を分析する。 ダウン症候群、エドワーズ症候群、パトー症候群などの主要な染色体異常を99%以上の高い精度で検出できる。 |
2. 侵襲的検査(流産リスクを伴う検査)
| 検査方法 | 妊娠週数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 絨毛検査(CVS) | 妊娠10~13週頃 | 腹部か膣から針を挿入し、胎盤の一部(絨毛)を採取して染色体異常や遺伝子異常を調べる確定診断。流産リスクが1~2%程度。 |
| 羊水検査 | 妊娠15~18週頃 | 腹部から細い針を刺して羊水を採取し、染色体異常全般を調べる確定診断。流産リスクが0.1~0.3%程度。 |
| 臍帯血採取(PUBS) | 妊娠18週以降 | 超音波ガイド下で胎児の臍帯(へその緒)に針を刺し、血液を採取して分析。他の検査で診断が困難な場合や緊急性がある場合に行われる。流産リスクは約1~2% |
出生前診断で陽性の結果が出た場合には、妊婦さん、パートナーは妊娠継続か中絶かという難しい選択を迫られることがあります。
そのため、遺伝カウンセリングや主治医からの説明で疑問を解消し、流産リスクのある検査や中絶への思いなど二人でよく話し合うことが大切です。
以下のよくある質問もぜひ参考にしてください。
中絶に関するよくある質問

出生前診断後に中絶ができるのはいつまでですか?
出生前診断で陽性の結果が出た場合に、「中絶はいつまでできるのか」という中絶の期限に関する質問は多く聞かれます。
中絶ができる期限は、母体保護法により妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)と定められています。
中絶ができる期間や、期間が過ぎた時の対処法を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:中絶はいつまで可能?期間が過ぎた時の対処法と手術の種類を解説
初期中絶と中期中絶の違いは何ですか?
中絶手術は妊娠週数によって「初期中絶」と「中期中絶」に分けられ、方法や身体的負担、費用などが大きく異なります。
| 項目 | 初期中絶 | 中期中絶 |
|---|---|---|
| 妊娠週数 | 妊娠6週ころ〜11週6日まで | 妊娠12週〜21週6日まで |
| 手術方法 | 吸引法や掻爬(ソウハ)法 | 陣痛促進剤を使用し、出産と同じ方法 |
| 所要時間 | 手術約15分(来院から帰宅まで3~4時間) | 1泊以上の入院が必要 |
| 痛み | 麻酔により術中の痛みはほとんどなし | 出産と同様の陣痛の痛みあり |
| 身体への負担 | 比較的少ない | 大きい |
| 回復期間 | 短い | 長い |
| 費用 | 7万円~10万円 | 30〜50万円 |
| 手術後の公的手続き | 特になし | 死産届の提出や埋葬が必要 |
妊娠9週0日までの中絶では、内服薬による中絶が可能な医療機関もありますが、日本では所要時間の短さや成功率の高さから、現在も手術による中絶が一般的になっています。
出生前診断の結果によって中絶を検討する場合、確定診断の検査は妊娠15週以降に行われるため、多くの妊婦さんが中期中絶を受けることになります。
中期中絶は初期中絶に比べて身体的・精神的負担が大きく、費用も高額になる傾向があります。
中絶についても、医師から十分な説明を受け、疑問や不安をできる限り解消して決断することが大切です。
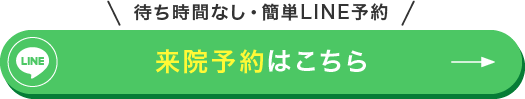
中絶手術の費用はどのくらいですか?
当クリニックでは妊娠11週までの初期中絶のみの実施となり、費用は以下の通りです。
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初診料(超音波検査、血液検査) | 16,500円 |
| 初期中絶手術費用 | 92,400円〜 |
| 術後の診察(1回目) | 0円 |
| 術後の診察(2回目) | 0円 |
人工妊娠中絶は原則、保険適用外の自費診療となるため、全額自己負担となり、妊娠週数や医療機関、麻酔方法などによって異なります。
| 妊娠期間 | 手術費用の相場 |
|---|---|
| 初期(妊娠11週まで) | 7~10万円 |
| 中期(妊娠12週から21週まで) | 40~60万円(入院・埋葬費用を含む) |
中絶手術の費用の詳細を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:中絶費用の平均・相場は?初期と中期による違いや払えない場合の対処法を解説
参考元:出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
まとめ
出生前診断で陽性結果が出た場合の中絶については、母体保護法やそれぞれの出生前検査の適応時期のもと、以下のポイントがあります。
- 日本では胎児の異常を直接の理由とした中絶は認められていませんが、母体の健康への影響という観点で母体保護法により事実上、中絶が認められています。
- 中絶が可能な期間は、妊娠21週6日まで。22週を過ぎるといかなる理由があっても中絶は認められません。
- 出生前診断には流産リスクのない非侵襲的検査(NIPT、超音波検査など)と流産リスクを伴う侵襲的検査(羊水検査、絨毛検査など)があります。
- 検査の種類によって実施時期や結果判明までにかかる期間が異なります。
- 羊水検査などの確定診断は20週前後になって結果が出る場合もあるため、21週6日までの中絶の期限との時間的な制約をあらかじめ知っておくことが大切です。
- 中絶は基本的に保険適用外の自費診療となり、妊娠週数によって費用が大きく異なります。
- 妊娠12週以降の中期中絶の場合は出産育児一時金の対象となる可能性があります。
- 出生前診断で陽性結果が出た場合の選択は、医学的情報だけでなく、個人の価値観や家族のサポート状況、経済的要因など多くの要素を考慮する必要があります。
- 遺伝カウンセリングなどの専門的なサポートを受けながら、十分な情報と話し合いのうえで意思決定することが大切です。
出生前診断と中絶は非常にセンシティブな問題であり、個々の患者さんの状況や価値観によって選択は異なります。
どのような選択をする場合でも、主治医や認定遺伝カウンセラーなどの専門家からの十分な情報提供と心理的なサポートを受けることが大切です。
妊婦さんとご家族が、それぞれの状況に応じた最善の選択ができるよう、この記事を通じて応援しています。