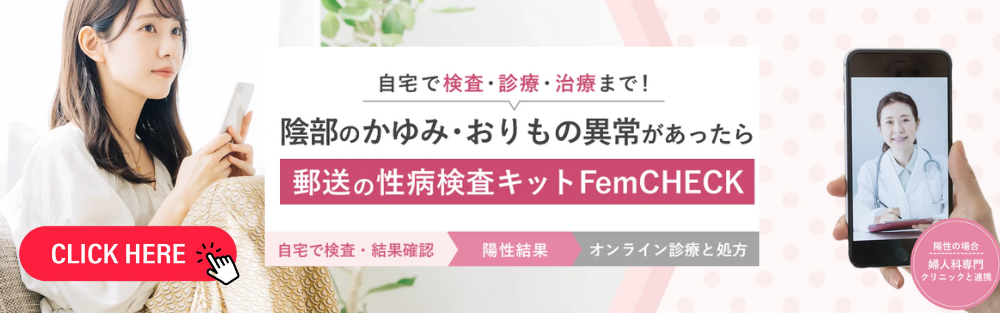中絶手術後になりやすい病気や症状には、感染症や子宮の損傷、出血過多、精神症状などが挙げられます。
これらのリスクは、術後の適切なケアや、定期健診の受診などによって減らすことが可能です。
また、中絶後の不妊リスクを心配している方も多いかもしれませんが、一度の中絶手術で不妊になる可能性はほとんどありません。
この記事では、中絶手術後に起こりうる病気や後遺症、不妊の可能性などについて詳しく解説します。
中絶手術後に起こりうる病気の種類と症状

中絶手術後に起こりうる病気には、主に次のようなものが挙げられます。
- 感染症(子宮内膜炎、骨盤腹膜炎など)
- 子宮損傷(子宮穿孔、子宮頚管損傷など)
- 出血過多
- 精神的な後遺症(うつ病、PTSDなど)
これらの病気を放置していると、重症化したり緊急手術が必要になったりする可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。それぞれの病気の特徴や初期症状、受診の目安などについてみていきましょう。
感染症(子宮内膜炎、骨盤腹膜炎など)
中絶手術後は、「子宮内膜炎」や「骨盤腹膜炎」といった感染症を発症する可能性があります。
感染症の初期症状としては、発熱や腹痛、悪臭のある帯下(おりもの)などが挙げられ、重症化すると高熱や吐き気、全身のだるさといった症状を引き起こす可能性もあります。
感染症の治療法としては、抗生物質の投与が一般的です。
手術後に継続的な出血がみられる場合は、感染症のリスクが高まる恐れがあるため、出血が止まるまでは清潔なナプキンにこまめに交換し、湯船には浸からないようにしましょう。
腹痛が続く場合も、感染症のサインである可能性があります。
我慢できない痛みに発展したり、発熱したりする場合にはすぐに医師に相談しましょう。
子宮の損傷(子宮穿孔、子宮頚管損傷など)
頻度は少ないものの、中絶手術の影響で子宮に穴があいたり(子宮穿孔)、子宮の入り口部分が傷ついたり(子宮頚管損傷)する可能性があります。
子宮が損傷すると、腹痛や出血といった症状や、感染症などを引き起こす恐れがあります。
治療法は損傷の程度によって異なりますが、一般的に行われるのは止血処置や抗生物質の投与、損傷部位の修復手術などです。正しい処置方法で手術が行われれば、術後に不妊症になることはほとんどありません。
また、中絶手術により「手術跡が残るのではないか」と心配される方もいるかもしれませんが、中絶手術の経験を外見だけで判断することは医師であっても難しいとされています。
開腹手術のように体の表面に傷が残るわけでもないので、周囲に知られる可能性も低いでしょう。
中絶手術を受けた事実や手術の内容などは、原則として医療機関で記録として保管されます。
ただし、医療記録は個人情報保護法に基づいて厳重に管理されているため、本人の同意なく第三者に開示されることはありません。
出血過多
個人差はあるものの、術後は生理のときのような出血が1~2週間程度続きます。
出血量は、おりもの程度の少量の場合もあれば、生理2日目のような量が出るケースなどさまざまです。
出血自体は術後によく見られる症状ですが、生理用品を1時間ごとに交換する必要があるほどの大量出血や、激しい腹痛を伴う場合などは、緊急性が高い可能性があります。
鮮血が止まらない場合も、子宮内での出血が続いている可能性があるため、すみやかに手術を受けた医療機関を受診しましょう。
精神的な後遺症(うつ病、PTSDなど)
中絶手術に対する不安や恐怖、罪悪感などから心に大きな負担がかかり、精神的に不安定になるケースがあります。
中絶手術後に起こりうる精神症状は、主に次のとおりです。
- うつうつとした気分
- 不安感
- 自己嫌悪
- 不眠
- 食欲不振 など
また、なかには「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」を発症する場合もあります。
中絶後の精神症状が続く期間には個人差がありますが、数週間~1年以上続くこともあるとされています。
上記のような症状が出た場合は一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しましょう。
医師やカウンセラーなどの専門家による支援を受けることも、自身の気持ちを整理し、心身の健康を取り戻すために有用な対処法のひとつです。
中絶手術後の不妊リスクと将来の妊娠への影響

「中絶手術を受けたら子どもを産めなくなるのでは?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、中絶手術によって不妊になる可能性は非常にまれです。
ここからは、中絶が将来の妊娠に与える影響や、不妊リスクを下げる方法について解説します。
中絶後の不妊リスクが気になる方は、下記の記事も参考にしてみてください。
関連記事:一度中絶すると妊娠しにくい?後遺症や中絶履歴が残るか解説
不妊症のリスク
一度の中絶手術が原因で、将来不妊症になることは極めてまれです。
手術中に子宮が傷つき、将来の妊娠に影響する可能性もゼロではありませんが、適切な医療機関で手術を受ければほとんどの場合で安全に処置が完了します。
中絶手術後の不妊リスクを最小限に抑えるためには、信頼できる医療機関の選択や、感染予防をはじめとする術後ケア、ストレスの軽減などが大切です。
不妊の原因には、「ホルモンバランスの乱れやストレスによる排卵障害」「子宮内膜症や子宮筋腫などの病気」「男性側の問題(精子の質や量)」など、さまざまなものがあります。
術後、避妊をしていないにもかかわらず1年以上妊娠しない場合は、不妊の可能性があるため産婦人科の専門医に相談しましょう。
H3.次回妊娠時の注意点
基本的に、中絶手術後から2週間は性交渉禁止です。
中絶手術の直後は排卵時期と重なる可能性が高く、妊娠しやすいためです。
妊娠を望まない場合は、コンドームやピルの使用といった適切な避妊対策を徹底しましょう。
中絶手術後すぐに妊娠を望む方は少ないかもしれませんが、もし希望される場合は、体を十分に休める意味でも、術後に生理が3回程度来てから妊娠を計画することが推奨されます。
中絶手術後のケアと注意点

中絶手術後は、身体と心の両面での十分なケアが必要です。
術後1週間程度は、激しい運動や重たいものを持ち上げることなどは避け、体を休ませましょう。
中絶手術後はとくに体を清潔に保ち、感染予防に努めることも重要です。
また、術後は罪悪感や後悔、不安などのさまざまな感情が湧き上がってくるかもしれません。
このような感情を抱くことは異常なことではないため、信頼できる人に話を聞いてもらったり、カウンセリングを受けたりと、心のケアも積極的に行いましょう。
術後の安静期間と日常生活の注意点
術後は激しい運動や立ち仕事などは避け、最低でも3日間は安静に過ごす必要があります。
感染症予防のために、医師の指示があるまでは入浴はシャワーのみにしましょう。
飲酒は出血のリスクを高める恐れがあるため、術後2週間程度(子宮がもとの状態に戻るまでの期間)は控えることが推奨されます。
性交渉についても、基本的に術後2週間は禁止です。
中絶手術のあとは排卵時期と重なる場合が多く、妊娠しやすい時期であるため、性交渉の再開時にはコンドームの使用やピルの服用などによる避妊対策をしっかり行いましょう。
定期検診の重要性
術後の定期健診では、出血や痛み、子宮の状態などを確認します。
万が一、術後に感染症やその他の合併症などが起こった場合でも、定期検診で見つかればすぐに治療を開始できます。
定期検診を受けない場合、感染症をはじめとする合併症に気づかず、症状が重症化したり、将来の妊娠に影響が出たりする可能性も否定できません。
重大なトラブルになってからでは遅いため、術後の定期健診は必ず受けるようにしましょう。
まとめ
中絶後は、感染症や子宮の損傷、出血過多、精神症状といったトラブルが生じる可能性があります。
しかし、近年の医療技術の進歩の影響もあり、適切な医療機関で手術を受ければ、このようなリスクが生じることはまれです。
万が一、術後に感染症や後遺症が起こったとしても、定期健診を受けることで早期発見・早期治療が可能です。
また、中絶手術による不妊リスクは極めて低いため、過度な心配は必要ありません。
術後はむしろ妊娠しやすいとされているため、妊娠を望まない場合は避妊対策を徹底するようにしましょう。