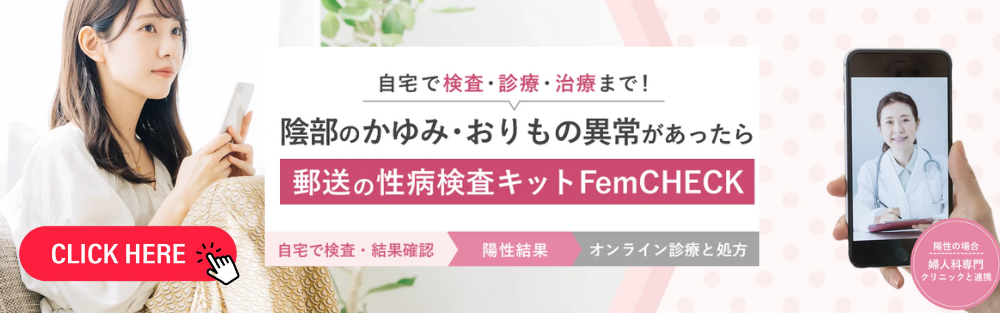中絶手術を初めて受ける際には、手術の流れや必要な準備、術後の生活など、さまざまな疑問や不安を感じることでしょう。
分からないことが多いと、漠然とした不安や恐怖で現実から目をそむけたくなり、積極的な行動が難しくなってしまいますね。
この記事では、中絶手術全体の流れから当日の持ち物、術後に気をつけるポイントまで解説しています。
正しい知識を知ることで不安や疑問を少しでも解消し、落ち着いて中絶手術に臨めるよう、ぜひご一読ください。
日帰り中絶手術の流れ

中絶手術は、妊娠初期(12週未満)であれば、ほとんどの場合、日帰りで受けることができます。基本的な流れは以下のとおりです。
それぞれの流れについて、詳しく見ていきましょう。
初回診療
妊娠に気がついたら、まずは産婦人科で診療を受けましょう。
中絶を検討している場合の初回診療は以下のような流れで進みます。
多くの医療機関では、WEBや電話での事前予約ができます。
予約時には「中絶について相談したい」と伝えるとスムーズに予約ができるでしょう。来院時には保険証や身分証明書(免許証など)を忘れずに持参してください。
受付で問診票を記入します。
以下の内容についてあらかじめ確認しておきましょう。
- 最終月経の期間
- 性行為の日付
- 過去の妊娠・出産歴
- 持病やアレルギー
診察では、問診票の確認と以下の検査が行われます。
・血液検査
梅毒などの性感染症や貧血の有無、血液型などを確認します。
・経腟超音波(エコー)検査
子宮内の胎嚢(たいのう)や胎児の有無、大きさを確認します。正常な妊娠かどうかや妊娠週数を診断します。
・膣分泌物の検査
クラミジアや淋菌などの性感染症の有無を確認します。
診察の結果をもとに、医師から以下の説明があります。
- 妊娠週数の確認と中絶可能な時期
- 手術の方法
- 手術にかかる費用
- 手術に伴うリスクや注意点
- 手術後の過ごし方について
疑問や不安があれば、遠慮なく医師に質問しましょう。説明を理解し、中絶手術に同意される場合は同意書を記入し、提出します。
中絶をするかどうかを迷っている場合は、いつまでに決めればよいか、医師と相談することもできます。
中絶手術を受ける意思が固まったら、手術日の予約を行います。
初回診療から手術日までの期間は、妊娠週数や医療機関の状況によって異なりますが、1、2週間程度空けることが多いようです。
妊娠週数が進んでいる場合や、患者さんの状況によっては初回診療当日に中絶手術を行う(即日中絶)場合もあります。
※即日中絶は、医療機関の状況で実施できる場合とできない場合があります。
会計窓口にて料金をお支払いください。
中絶手術当日
手術の当日の流れについて詳しく見ていきましょう。
日帰りの中絶手術の場合、来院から帰宅までの所要時間は、3~5時間程度が一般的です。
予約時間に来院し、受付を済ませて中絶費用を支払います。
手術前の体調を確認します。つわりなど体調不良がある場合は必ず伝えてください。
手術前の準備で、以下のことが行われます。
- 体温、血圧、脈拍を計測する
- 手術用のガウンに着替える
- トイレで排尿を済ませる
中絶手術の痛みを和らげる麻酔には、以下の方法があります。
・局所麻酔
子宮頸部に麻酔薬を注射して痛みを抑えます。
・静脈麻酔
点滴から麻酔薬を投与し、意識がある状態で痛みを感じなくします。
・全身麻酔
完全に眠っている状態で手術を行います。(全身麻酔に対応している医療機関は限られます)
麻酔の方法は医療機関によって異なりますので、不安がある場合は事前に確認しておきましょう。
手術中は麻酔の効果で眠っているか、意識はあっても痛みは感じにくい状態です。
手術は、通常15分程度で終わります。
初期の中絶では、以下のいずれかの手術方法で行われます。
・吸引法
子宮内の胎児や胎盤を吸引器で吸い出す方法。
吸引法はWHOでも推奨されている安全性の高い方法といえます。※1
・掻爬(そうは)法
子宮内の内容物をスプーン状の器具でかき出す方法。日本では従来から多く行われています。
・両方の併用
吸引法で大部分を取り出した後、掻爬法で残りを確実に除去する場合があります。
手術後はベッドで2〜3時間ほど休みます。
看護師が出血の状態や痛み、血圧や脈拍数、麻酔からの覚醒状態などを確認します。
回復を促すために水分や軽食を摂ってもらうこともありますが、自己判断で飲食せず、医師や看護師に確認しましょう。
医師による術後診察を受けます。手術後の過ごし方や異常時の連絡先についても説明があります。
診察で異常がなければ、術後検診の予約と処方薬の受け取りを済ませて、帰宅できます。
処方薬は、以下のものが一般的です。
- 抗生物質(感染を予防する)
- 子宮収縮剤(子宮の戻りを良くして出血を抑える)
- 鎮痛剤(術後の痛みの緩和)
症状や過ごし方、服薬などで疑問や不安があれば、遠慮なく医師に質問しましょう。
※1引用元:WHO|リプラ&日本助産学会訳|中絶ケアガイドライン エグゼクティブサマリー
※引用元では初期中絶の週数として「14週未満」と記載がありますが、日本では戸籍法にて「12週以降の死児の出産」を「死産」と規定し、初期中絶は11週までの適用となります。
中絶手術後
中絶手術後の流れや気をつけるポイントについて解説します。
・出血
手術当日から1〜2週間程度、生理のような出血が続きます。最初の数日間は出血量が多く、徐々に減少していきます。
・痛み
子宮の収縮により、生理痛のような痛みが生じます。我慢せずに処方された鎮痛剤を使用しましょう。
以下の症状がある場合は、術後診察まで待たずに手術を受けた医療機関に連絡しましょう。
- 大量の出血(1時間で夜用ナプキンを1枚以上交換する)
- 立っていられないほど強い腹痛がある
- 39℃以上の発熱
- 出血に悪臭がある
術後の回復を促すために、日常生活では以下のことに注意しましょう。
・安静
手術当日から数日間はなるべく安静に過ごしましょう。特に重い物を持つことや、激しい運動は控えてください。
・入浴
シャワーで済ませ、湯船につかるのは術後1週間程度避けましょう。
・性行為
感染リスクを避けるため、術後検診までは控えてください。
・仕事や学校
体調が良ければ、軽作業やデスクワークなら手術の翌日から復帰できます。重労働や立ち仕事は1週間ほど休むことをおすすめします。
中絶手術後は身体的な回復だけでなく、心理的なケアも重要です。
罪悪感や悲しみなど、様々な感情が生じることがあり、我慢せずに思いを話すことも大切です。
中絶手術を行っている医療機関では、中絶後のメンタルケアや相談先の紹介などの対応をしてくれますので、一人で抱え込まずに相談してみましょう。
術後検診では、内診や超音波検査で以下のことを確認しています。
- 子宮の回復状態
- 出血の状況
- 感染の有無
不安なことや気になる症状があれば、この機会に相談しましょう。
特に、性行為を再開できる時期と排卵の時期が重なりやすいため、ご自身に合った避妊方法について医師と相談しましょう。
中絶手術当日に必要な持ち物

中絶手術をスムーズに受けられるように、一般的な持ち物や身支度などの準備等を解説します。
医療機関によって必要な持ち物は異なる場合がありますので、手術を受ける医療機関の持ち物を事前に確認しておきましょう。
- 健康保険証…中絶手術は保険適用外ですが、術前検査などで必要になることがあります。
- 身分証明書…健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど。
- 同意書…事前に医療機関から渡された同意書に必要事項を記入し、捺印したもの。
- 手術費用…現金のほか、クレジットカード対応の医療機関も増えています。
- 診察券
- お薬手帳…常用している薬がある場合
- 夜用の生理用ナプキン…手術後の出血に備え、3枚~5枚程度、多めに持参すると安心です。
- 生理用ショーツ
- ヘアゴム…髪の長い方は、手術中結んでおきましょう。
- 飲み物・軽食…手術後に飲食できる場合があります。手術を受ける医療機関で確認しましょう。
配偶者の同意については母体保護法に定められており、同意書には配偶者・パートナーのサインも必要です。また、手術を受ける方が未成年の場合は、保護者の同意書も必要となります。
ただし、
前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
厚生労働省|母体保護法|第14条
という記載もあり、性被害での妊娠や相手が不明な場合など、相手のサインを省略できる場合もあります。
中絶手術当日に持っていくと便利なもの
- カーディガンなど室温や体感に合わせて着脱できるもの。
- 筆記用具…医師からの説明や聞きたいことをメモしておきましょう。
- スマートフォン…待ち時間や術後の休憩時間に使用できます。
持ち物以外の事前準備
中絶手術の数日前〜当日までに、以下の準備をしておきましょう。
- マニキュア・ネイルの除去…手術中の機器装着や観察のためマニキュアやジェルネイルは事前に除去しておきましょう。
- 帰宅手段の手配…手術後は麻酔の影響で車の運転はできません。家族やパートナー、信頼できる友人に送迎を依頼したり、タクシーの配車予約をしたりしておくと、より安心でしょう。
手術をスムーズに受けるためには、いくつかの準備が必要です。
麻酔を受けるため、手術6時間前からの絶食、3時間前からの水分摂取制限が一般的です。手術を受ける医療機関の案内を確認し、飲食制限の開始時間にアラームをかけておくなど、時間を守れるように工夫しましょう。
また、手術中・手術後の体調を観察するときに顔色や唇の色も確認するため、薄化粧かすっぴんでの来院がおすすめです。
手術後は出血や下腹部の痛みが予測されますので、着替えやすいゆったりとした服装での来院がおすすめです。また、アクセサリーは手術中は外しますので、最小限にしましょう。
中絶手術に関するよくある質問

中絶手術を検討する際には、さまざまな疑問や不安があるものです。ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
中絶手術の費用はいくらですか?
中絶手術は健康保険が適用されないため、以下のように費用の相場も高額になる傾向があります。
| 妊娠期間 | 手術費用の相場 | 術前・術後診察費用 | 合計 |
| 初期(11週まで) | 7~10万円 | 2万円 | 9万円~12万円 |
| 中期(12週から21週まで) | 40~60万円(入院・埋葬費用を含む) | 2万円 | 42万円~62万円 |
妊娠週数が進むほど費用は高くなり、特に12週を超える中期中絶では入院が必要となるため、費用が大幅に上がります。
中絶費用について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:中絶費用の平均・相場は?初期と中期による違いや払えない場合の対処法を解説
中絶手術を受けたら、妊娠しにくくなるのでしょうか。
母体保護法指定医のいる医療機関で中絶手術を受けた場合、将来の妊娠への影響はほとんどありません。
現代の中絶手術は安全な方法が確立されているため、初期中絶では子宮に与えるダメージを最小限に抑えられます。特に、WHOが推奨する吸引法は、子宮内膜への影響が少なく、手術後の回復も早いのが特徴です。
ただし、以下の場合は将来の妊娠に影響する可能性があります。
- 手術後の感染症
- 複数回の掻爬法による中絶
- 母体保護法指定医によらない違法な方法での中絶手術
これらのリスクを最小限に抑えるためには、以下のポイントが重要です。
- 手術後の服薬や性行為の禁止期間など、医師の指示を守り、感染症を予防する
- 術後検診を受診し、避妊の相談をする
- 母体保護法指定医のいる医療機関を選ぶ
将来の妊娠について不安がある場合は、産婦人科医に相談してみましょう。
中絶手術後、生理はいつ来ますか?
中絶後、生理が再開するまでの期間は個人差がありますが、一般的には手術から1〜2ヶ月後が多いようです。
中絶手術で妊娠が終わると、体内のホルモンバランスが妊娠前の状態に戻っていき、新たな月経周期が始まります。
生理再開までの期間の長さは、年齢や、妊娠週数、中絶後のピル服用の有無、ストレスなど、さまざまな要因で変化しますが、遅くても3~4ヶ月以内に再開するのが一般的です。
中絶手術後4ヶ月以上経っても生理が来ない場合や、不規則な出血が続く場合は、中絶手術を受けた医療機関に相談、受診をしましょう。
まとめ
中絶手術の流れには「初回診療」「手術当日」「術後の検診とケア」があり、それぞれの具体的な内容や注意点について解説しました。
手術当日の持ち物や事前準備は一般的な内容をご紹介していますので、手術を受けられる医療機関でも確認しましょう。
手術後は医師の指示を守ることはもちろん、無理をせずに休息をとること、思いを我慢せずに話すことも回復の一助となるでしょう。
中絶手術が将来の妊娠能力に影響を与える可能性は低く、望まない妊娠を繰り返さないように、ご自身に合った避妊方法を産婦人科医と相談することも大切です。
最後までお読みいただきありがとうございます。疑問や不安を減らし、スムーズな受診・手術にお役立ていただければ幸いです。