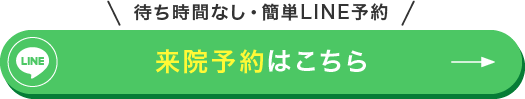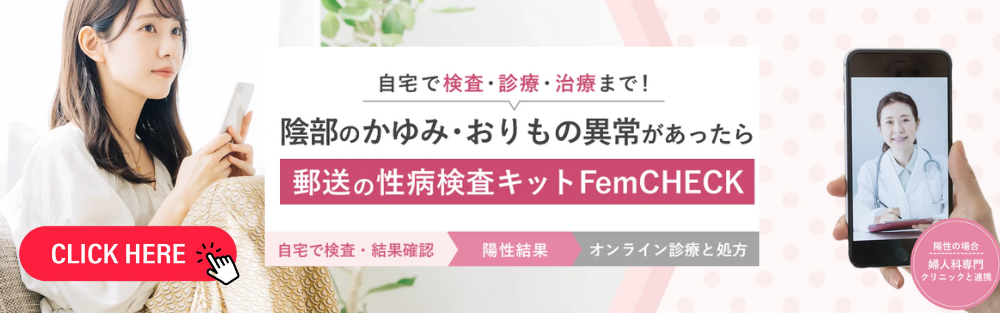「生理前になるとだるくて何もしたくない…」「毎月気分が落ち込む」と感じる方も多いのではないでしょうか?実はその不調、PMS(月経前症候群)が原因かもしれません。
ホルモンバランスの変化によって心や体が敏感になり、疲れやすくなるため、自然とやる気が出にくくなる時期です。「だるい=甘え」と捉えず、体が休息を求めているサインと受け止めましょう。
この記事では、PMSのメカニズムやPMDDとの違い、そしてだるさを和らげるための具体的な対策方法を詳しく解説。体を温める習慣や食事・睡眠のポイントも紹介しています。自分の体と向き合い、心地よく過ごすためのヒントを見つけましょう。
PMS(月経前症候群)とは?

女性の多くが月経の約1〜2週間前に経験するPMS(月経前症候群)は、ホルモンバランスの変動によって心と体のリズムが崩れることが主な原因です。
エストロゲン(卵胞ホルモン)の減少とプロゲステロン(黄体ホルモン)の増加が関係しています。これらのホルモンの変化が、自律神経や脳内の神経伝達物質に影響を与えるため、「だるい」「イライラする」「気分が落ち込みやすい」といった症状が起こります。
また、PMSは一時的な不調ではなく、生活の質を左右するほど強く出ることも。しっかり原因を理解して、自分の体に合ったケアを行うことで、症状の軽減や予防が可能です。以下では、それぞれのホルモン変動による影響を詳しく解説します。
エストロゲン(卵胞ホルモン)の減少の影響
エストロゲンは、女性の心と体のバランスを整える重要なホルモンです。
排卵を過ぎて月経が近づくと、その分泌量が急激に低下。この変化がPMS(月経前症候群)で感じる「気分の落ち込み」や「体のだるさ」を引き起こす大きな要因になります。
エストロゲンが減ることで、幸せホルモンであるセロトニンの分泌も低下し、心の安定が保ちにくくなります。この時期に起こりやすい体調変化は以下の通りです。
- 自律神経の乱れ
- イライラや情緒不安定
- 眠気・集中力の低下
プロゲステロン(黄体ホルモン)の増加の影響
排卵後から月経前にかけて増加するプロゲステロンは、妊娠の準備を整えるホルモンです。体を「休息モード」に導く働きがある一方で、代謝を鈍らせたり体温を上げたりするため、「だるい」「疲れやすい」といった症状が出やすくなります。
また、プロゲステロンは水分をため込みやすくする作用があり、むくみや胸の張りといった不快感も伴うことがあります。 この時期に見られやすい体の変化は次の通りです。
- 強い眠気やだるさ
- 胸の張り
- むくみ
- 便秘
- 肌荒れ
症状が重い場合はPMDDの可能性もある
生理前のイライラや不安、気分の落ち込みが日常生活に支障をきたすほど強い場合は、PMSではなく「PMDD(月経前不快気分障害)」の可能性があります。PMDDは、PMSの中でも特に精神的な症状が重いタイプで、ストレスや人間関係に大きく影響することもあります。
主な症状としては次のようなものがあります。
- 強い抑うつ感や不安感
- 感情のコントロールが難しくなる
- 眠れない、または過眠になる
こうした症状は、自分の努力や気持ちの持ち方だけでは改善しにくいこともあります。もし「毎月つらくて仕事や生活がうまくいかない」と感じる場合は、婦人科やメンタルクリニックでの相談がおすすめです。適切な診断とケアによって、心身の負担を軽くすることができます。
PMSによるだるさの対策方法

生理前のだるさを感じる時期は、体と心のバランスが揺らぎやすいタイミングです。無理に「いつもの自分」に戻そうとするよりも、ホルモンバランスに寄り添ったケアを取り入れることが大切です。
ここでは、PMSによる「だるい」「何もしたくない」という不調をやわらげるための具体的な対策を紹介します。
体を温めて血流を改善する
PMSの時期は、ホルモンの影響で血行が悪くなり、冷えやだるさを感じやすくなります。体を温めることで代謝が上がり、全身にしっかり血液が巡るようになり、重だるい感覚が和らぐ効果が期待できます。特に手足の冷えを感じる方は、温熱系アイテムや入浴剤を活用しましょう。
- 入浴剤(炭酸ガス・ショウガ・トウガラシ配合)
- 腹部・腰まわりを温めるカイロ
- 腹巻き
PMSの冷え対策にはお腹を冷やさないことがポイント。温かい飲み物を意識的に取り入れ、体を内側から温め直すのもおすすめです。
軽い運動やストレッチを取り入れる
運動不足や血流の滞りは、PMSのだるさを悪化させる原因になります。ジョギングのような激しい運動ではなく、軽いストレッチやウォーキングなど「リラックスしながら体を動かせる運動」を選ぶのがおすすめです。血流とリンパの流れが良くなり、むくみの軽減にもつながります。
血流とリンパの流れが良くなり、むくみの軽減にもつながります。また、気分もリフレッシュされるでしょう。
十分な睡眠を心がける
ホルモン変動がある時期は、睡眠の質が低下しやすく、疲労感やだるさが強く出る傾向があります。
就寝前はスマホやPCの使用を控え、リラックスできる環境を整えましょう。睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を促すことで、体の回復力やホルモンバランスが整いやすくなります。
食事で血糖値の安定を意識する
生理前は食欲が乱れやすく、甘いものを無性に食べたくなる人も多いでしょう。これは血糖値が不安定になっているサイン。急上昇・急降下を繰り返すと、眠気や倦怠感が増してしまいます。
食事は「3食しっかり・ゆっくり噛む」を意識することがポイント。白米よりも玄米や雑穀米にしたり、たんぱく質や野菜を組み合わせることで、血糖値の波を穏やかに保てます。小腹が空いたときはナッツ類やヨーグルトなど、栄養価の高い間食を選ぶとよいでしょう。
精神の安定をサポートする栄養素を補給する
PMSの時期は、ホルモン変化により心を安定させる栄養素が消耗しがちです。特にビタミンB6、マグネシウム、カルシウムなどは、セロトニンの働きを助けるために欠かせません。食事から摂るのが難しい場合は、これらを含むサプリメントで補うのもおすすめです。
こうした栄養素を意識的に補うことで、気持ちの落ち込みやイライラ感を防ぎ、だるさを軽減できます。体だけでなく心の安定にもつながるため、気力が戻る実感を得られるでしょう。
婦人科で相談する
「毎月つらすぎる」「動けないほど疲れる」という場合は、自己ケアだけで抱え込まず婦人科へ相談しましょう。一見PMSに見える症状でも、PMDD(月経前不快気分障害)などの可能性があるため、医師のサポートが重要です。
相談することで、漢方や低用量ピルなど、自分の体質に合った治療法を提案してもらえることもあります。専門の視点から体の状態を知ることが、根本改善への第一歩です。
まとめ
生理前のだるさや気分の落ち込みは、ホルモンバランスの乱れによる自然なサインです。無理に気合で乗り切ろうとせず、「今は体を休める時期」ととらえて、自分をいたわることがいちばんのケアになります。
体を温めて血流を整えたり、軽い運動や十分な睡眠を意識したりするだけでも、不調は少しずつやわらいでいきます。
また、心の不安定さが続いたり、日常生活に支障が出るほどつらい場合は、婦人科や専門医に相談することも大切です。PMSやPMDDの重さは人それぞれ。自分に合った方法で無理なくケアしながら、毎月を少しでも穏やかに過ごしていきましょう。
ルナレディースクリニックは、低用量ピルや漢方薬の処方に対応しております。つらい症状にお悩みの場合は当クリニックにご相談ください。