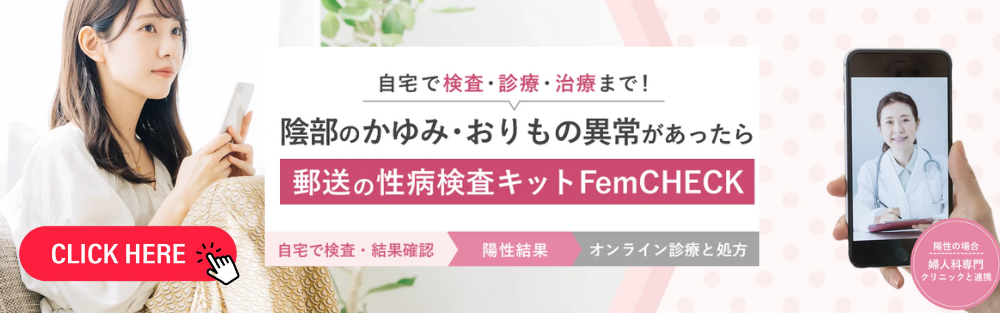「寝ても疲れが取れない」「午後になるとぼんやりして集中できない」――そんな悩みを感じていませんか?
それは、体ではなく“脳”が疲れているサインかもしれません。
本記事では、医学的にも注目される「脳疲労」の正体と、その原因・回復方法をわかりやすく解説します。
また、生活習慣だけでなく、不足しがちな栄養をサポートする手段として、医師監修のサプリメント「Rimenba(リメンバ)」もご紹介。
初回50%OFF+15日間返金保証(※クレジットカード決済限定)の公式キャンペーンを活用し、今日から脳をいたわる一歩を踏み出しませんか?
脳疲労とは?セルフチェックで今の状態を確認

「十分に寝たはずなのに、なぜか頭が重く感じる」「集中力が続かず、仕事でミスが増えている」――そんな経験はありませんか?
実はそのような状態は、肉体の疲れではなく、脳そのものの疲労によって引き起こされている可能性があります。
本章では、近年注目されている「脳疲労」の正体とメカニズム、そして今の自分の状態を確認できる簡単なセルフチェックをご紹介します。
脳疲労とは|脳の“使いすぎ”で処理機能がダウンする状態
脳疲労とは、脳の中でも主に前頭前野(前頭葉)が情報処理・意思決定・感情制御などを過剰に行い続けることで、神経機能のパフォーマンスが低下する状態です。
現代人は、スマートフォンやパソコンから膨大な情報を常時処理し、マルチタスクで判断を下す場面が多いため、無意識のうちに脳に大きな負荷をかけています。
特に脳のオーバーワークによって次のような現象が起こります。
- 認知機能の低下(思考力・集中力の減退)
- 情動の不安定化(イライラ・落ち込み)
- 自律神経の乱れ(睡眠障害・動悸など)
つまり、脳疲労は単なる“頭の疲れ”ではなく、心身全体に波及する慢性的な疲弊状態と言えるのです。
あなたは大丈夫?脳疲労セルフチェック10項目
以下のような症状に、いくつ当てはまるか確認してみましょう。
3項目以上当てはまる場合は、脳疲労の兆候が出ている可能性があります。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 集中力が続かない |
| 2 | 物事の判断に時間がかかる |
| 3 | 最近、物忘れが増えた |
| 4 | イライラしやすくなった |
| 5 | 頭がボーッとする時間が多い |
| 6 | 朝起きても疲れが残っている |
| 7 | 寝つきが悪い/夜中に目が覚める |
| 8 | 人と話すのが面倒に感じる |
| 9 | 仕事の効率が落ちたと感じる |
| 10 | 自律神経の乱れ(動悸・発汗など)を感じることがある |
このような症状は、単なる「忙しさ」や「加齢」のせいと片付けてしまいがちですが、脳の疲労がサインとして現れていることも少なくありません。
早めの対処によって、仕事や日常生活の質を大きく改善できる可能性があります。
脳疲労を招く5大原因
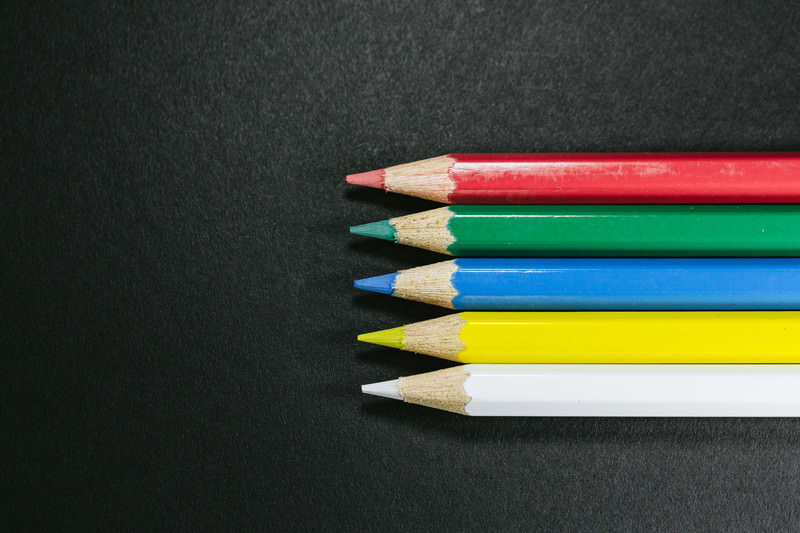
脳疲労は単なる「使いすぎ」だけでなく、現代のライフスタイル全体に根差した複数の要因が複雑に絡み合って発生します。
ここでは、脳に慢性的なダメージを与える代表的な5つの原因を解説します。
スマホ・PCの長時間使用|情報処理の負荷が限界を超える
現代人の生活に欠かせないスマートフォンやパソコンですが、画面から受けるブルーライトの刺激や通知による情報過多は、前頭前野に大きな負荷をかけています。
特にSNSやニュース、動画視聴など、絶え間なく情報を処理する習慣は、脳が休む時間を奪い、慢性的な疲労を招きます。
しかも、画面を見るだけでなく「返信すべきか」「いいねするか」など意思決定の積み重ねも、無意識に脳のエネルギーを消費しているのです。
睡眠不足・質の低下|脳の修復機会を奪う
厚生労働省の調査によると、日本人の約4割が1日6時間未満の睡眠しか取っていないと報告されています。
脳は睡眠中に情報整理や神経細胞の修復を行っており、慢性的な睡眠不足は脳疲労を蓄積させる最大の原因のひとつです。
また、睡眠の「質」が低い(夜中に目が覚める・寝つきが悪い)場合も、深いノンレム睡眠が確保できず、脳の回復力が落ちてしまいます。
マルチタスク・ストレス|脳が常に“フル回転”状態に
メール対応をしながら会議資料を作成し、SNS通知にも対応――このような「マルチタスク」は効率的に見えて、実際には脳の切り替え負荷が非常に高いことがわかっています。
同時進行の作業は、脳のエネルギー消費量を増加させ、集中力を著しく低下させるのです。
さらに、日常的なストレスによって分泌されるストレスホルモン(コルチゾール)は、脳の記憶や感情をつかさどる海馬にダメージを与えるといわれています。
栄養不足(糖・ビタミン)|脳は“食べる臓器”
脳は体重の約2%しかない臓器でありながら、1日に消費するエネルギーは全体の約20%にものぼるといわれています。
その主要なエネルギー源が「ブドウ糖」です。加えて、神経伝達物質の合成や修復にはビタミンB群が欠かせません。
しかし、忙しい日々の中で炭水化物を極端に制限したり、外食中心の生活が続いたりすると、脳が必要とする栄養素が慢性的に不足し、回復力が落ちてしまいます。
運動不足|血流低下で酸素と栄養が届かない
適度な運動は、筋肉や心肺機能だけでなく、脳の健康維持にも効果があるとされています。
なかでも有酸素運動は、脳内の血流を促し、酸素や栄養素を神経細胞へ届ける働きがあると考えられています。
一方、運動不足が続くと脳への血流が滞り、情報処理スピードや集中力が落ちるだけでなく、認知機能の衰えにつながる可能性もあるでしょう。
今すぐできる脳疲労回復法9選

脳疲労の蓄積を放置すると、集中力の低下や判断ミスを引き起こすだけでなく、心身全体の不調につながるおそれがあります。
しかし、生活の中に少し工夫を取り入れるだけで、脳の回復力を高めることは十分可能です。
ここでは、今日から取り組める即効性と実践性のある回復法を9つご紹介します。
入浴|40℃のお湯に10分つかる
仕事終わりや寝る前に、湯船にしっかりつかる習慣はありますか?
40℃程度のお湯に10分ほど浸かると、体の深部体温が上がり、全身の血行が促進されます。
これにより、脳へ酸素や栄養が届きやすくなり、ぼんやりした感覚も自然と抜けていきます。
一方でシャワーだけで済ませる日が続くと、緊張状態が続きやすく、睡眠の質も低下しかねません。
疲れを感じたときほど、浴槽に入って“脳を休ませる”時間を意識したいところです。
深呼吸|1分でもリセット効果あり
頭が重く、考えがまとまらないときは、いったん立ち止まって深呼吸をしてみてください。
鼻からゆっくり吸って、口から時間をかけて吐く。この腹式呼吸を数回行うだけでも、自律神経の働きが整い、脳の疲れが軽くなる感覚を得られることがあります。
ポイントは「静かな場所」「姿勢を正す」「1分でいいから集中する」の3つ。
慌ただしい毎日の中でも取り入れやすい、シンプルで効果的なリセット法です。
デジタルデトックス|“何もしない時間”を意図的につくる
スマホやパソコンに触れ続ける日常の中で、脳は休む暇もなく働き続けています。
とくにSNSや動画などは刺激が強く、前頭葉の情報処理機能をフル稼働させてしまいます。
1日15分でもいいので、画面を見ない“何もしない時間”を意識してつくることが大切です。
寝る前にスマホを見ない習慣をつけると、睡眠の質が上がり、脳疲労の回復もスムーズになります。
軽い運動|15分のウォーキングでOK
身体を動かすと、筋肉だけでなく脳にも良い刺激が届きます。
特にウォーキングのような軽い有酸素運動は、脳の血流を促し、前頭葉の働きをサポートするといわれています。
集中力が切れてきたと感じたら、室内にこもらず、少し外を歩いてみましょう。
たとえ15分でも、気分転換と脳のリフレッシュを同時に叶えることができます。
通勤中に一駅分歩く、昼休みに公園を一周するなど、日常の中に取り入れる工夫がポイントです。
ストレッチ|首や肩をゆるめて血流アップ
デスクワークやスマートフォンの操作が続くと、無意識のうちに首や肩が固まってきます。
この状態が続くと、脳への血流が滞り、集中力や思考力の低下につながる恐れがあるのです。
こまめに首を回したり、肩甲骨を動かしたりするだけでも、筋肉がほぐれ、血流がスムーズになります。
1〜2時間ごとに軽いストレッチを挟むことで、疲労がたまりにくくなり、頭もすっきりして作業効率が上がるでしょう。
昼寝|20分以内がベスト
午後になると、どうしても眠気や集中力の低下を感じやすくなります。
そんなときは、20分以内の短い昼寝を取り入れてみてください。
この“パワーナップ”は脳の回復に効果的とされており、眠気をリセットし、作業の効率も高めてくれます。
30分を超えると逆に頭がぼんやりしてしまうため、アラームを使って時間を管理すると安心です。
昼食後や休憩時間などにうまく取り入れ、午後もシャキッとした状態で過ごしましょう。
マインドフルネス|“今ここ”に意識を向ける習慣
脳が疲れているときは、過去の後悔や未来の不安に思考が引っ張られがちです。
そうした雑念を一度リセットするのが、呼吸や感覚に意識を集中させるマインドフルネスの役割です。
深く呼吸しながら「いま自分が何を感じているか」に注意を向けるだけでも、脳の過活動が落ち着いていきます。
まずは1日5分、静かな場所で目を閉じてみましょう。
継続することで、ストレス耐性や集中力の向上も期待できます。
タスク整理|“1つずつ終える”だけで違う
複数の仕事を同時にこなそうとすると、脳は絶えず切り替えを繰り返すことになり、大きなエネルギーを消耗します。
これが脳疲労の一因になっているケースも少なくありません。
まずは、やるべきことを紙やアプリに書き出し、1つずつ順番に終わらせていくシングルタスクを意識しましょう。
「ひとつ終えるごとに達成感が得られる」「集中しやすくなる」など、効果を実感しやすい方法です。
良質な睡眠|“6〜7時間”を目標に
脳の回復にもっとも大切なのは、やはり睡眠です。
特に深いノンレム睡眠中には、神経の修復や老廃物の除去が進み、翌日の思考力や記憶力に直結します。
理想的な睡眠時間は6〜7時間。
ただし、時間だけでなく「質」も重要です。
寝る前にスマホを見ない、部屋の照明を落とすなど、入眠前の過ごし方を整えることで、眠りの深さが変わってきます。
眠りをおろそかにすると、脳疲労はなかなか回復しません。
食事と栄養で脳を根本サポート

生活習慣の見直しだけでは、脳の疲れを根本的に改善するのが難しいと感じる人も多いかもしれません。
そんなときに注目したいのが、「栄養」です。
脳は私たちが摂取した栄養を使って働いており、必要な成分が不足すると、判断力・記憶力・気分の安定などにも影響が出てきます。
ここでは、脳疲労対策として特に意識しておきたい栄養素と、その働きについて解説します。
ブドウ糖とビタミンB群|脳のエネルギー源と神経の回復に不可欠
脳は体重の2%しかありませんが、エネルギー消費量は全身の約20%を占めています。
その主な燃料となるのがブドウ糖で、1日に約120gが必要とされています。
また、神経の働きを助けるビタミンB群は、エネルギー代謝だけでなく、ストレス耐性の向上にも関わる重要な栄養素です。
過度な糖質制限や偏った食事が続くと、脳のパフォーマンス低下を招くおそれがあります。
DHA/EPA|記憶・判断力を支える“脳の油”
青魚に多く含まれるDHAやEPAは、いわゆる“良質な油”として知られています。
これらは脳の神経細胞の膜を柔軟に保つ働きがあり、情報の伝達をスムーズにする役割を担っています。
中でもDHAは、記憶や判断力をつかさどる海馬にも多く存在しており、脳の機能維持に欠かせない存在です。
しかし、現代の食生活では摂取量が不足しやすいため、意識的に補う必要があります。
抗酸化&血流系成分|イチョウ葉など植物由来の力にも注目
脳は酸素を大量に使う器官であるため、酸化ストレスの影響を受けやすいとされています。
そこで有効なのが、抗酸化作用を持つ栄養素や、血流をサポートする成分の活用です。
代表的なものとしてはイチョウ葉エキスがあり、ポリフェノールやフラボノイドが含まれています。
これらは血管を広げたり、毛細血管の流れをよくしたりすることで、脳全体の巡りをサポートします。
サプリで効率補給――Rimenba(リメンバ)がおすすめ!
脳に必要な栄養素は日々の食事から摂るのが理想ですが、現実にはなかなか難しいという声も多く聞かれます。
「忙しくて魚を食べる習慣がない」「食欲が不安定で栄養に偏りがある」など、生活スタイルによって補給できる栄養は偏りがちです。
そこで注目されているのが、脳のための成分をバランスよく配合したサプリメント。
中でも、脳神経内科医監修のサプリ「Rimenba(リメンバ)」は、1日4粒で必要な成分をしっかり補える設計となっています。
成分をオールインワンで厳選配合
Rimenbaは、脳の疲労に関わる研究で注目されている成分を複数配合しています。
栄養バランスや飲みやすさにも配慮されており、続けやすいのが特徴です。
【Rimenbaに含まれる主な成分と働き】
| 成分名 | 主な働き |
|---|---|
| DHA・EPA | 神経細胞の情報伝達をスムーズにし、記憶力や判断力を支える |
| イチョウ葉エキス | 血流をサポートし、酸素と栄養を脳全体へ届けやすくする |
| ビタミンB群 | 神経伝達物質の合成を助け、ストレス耐性や集中力を支える |
また、公式サイトで販売されている商品は粒が小さく、1日4粒でOK。
「飲みにくさが気になる」という方でも取り入れやすい仕様です。
初回50%OFF+500オフクーポンあり+15日間返金保証(※クレカ決済限定)
Rimenbaは、「まずは試してみたい」という方にも優しい購入制度が整っています。
現在、公式サイト限定で初回半額+返金保証付きキャンペーンを実施中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回価格 | 通常の50%OFF(定期コース初回) |
| 返金保証 | 15日間の全額返金保証(※クレジットカード決済限定) |
| 粒仕様 | 小粒タイプ(1日4粒)で継続しやすい |
| 購入方法 | 公式サイトからの申し込み限定 |
この制度があることで、「自分に合うか分からない」と感じる方でも気軽に始めやすくなっています。
なお、Amazonや楽天などからの購入では、上記の特典は受けられません。
脳疲労を放置すると?リスクと回復期間
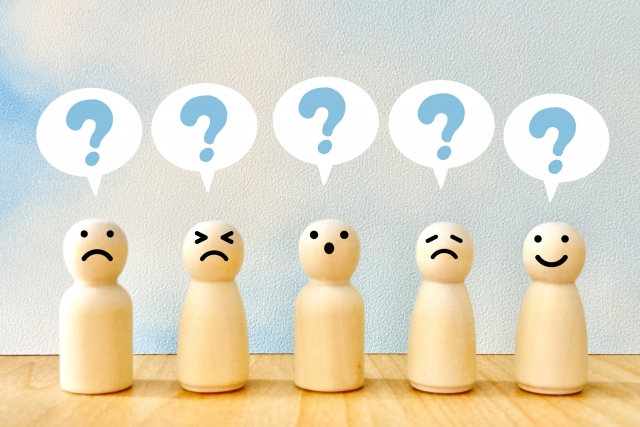
「ただの疲れ」と思って放置してしまいがちな脳の不調。
しかし、脳疲労は放っておくと、心身にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかっています。
集中力の低下やミスの増加といった日常的な支障だけでなく、メンタル面のトラブルや、慢性化による生活の質の低下にまでつながる可能性があります。
ここでは、脳疲労の放置によるリスクと、回復にかかる時間の目安について解説します。
認知機能の低下やうつ症状につながることも
脳疲労が慢性化すると、思考や感情に関わる領域がうまく働かなくなり、生活全体に影響を及ぼす可能性があります。
【放置によって現れやすい変化の例】
- 集中力が続かず、仕事や勉強の効率が落ちる
- ミスが増え、注意力が散漫になる
- 感情の起伏が激しくなり、人間関係が不安定に
- 不眠や食欲不振など、自律神経の乱れが出てくる
- 抑うつ状態や不安感が強まり、心の調子も崩れる
違和感を感じた段階でケアを始めることが、深刻化を防ぐ第一歩です。
回復には数日〜数週間、慢性化すれば数ヶ月単位も
脳疲労の回復にかかる時間は、疲労の程度や生活環境によって変わってきます。
短期間でリカバリーできるケースもあれば、何ヶ月もかかることもあります。
【回復までの目安】
- 軽度の場合:2〜3日の休養や睡眠の改善で回復
- 中等度:1〜2週間の生活改善+栄養サポートが必要
- 慢性化した場合:数ヶ月にわたり根本的な見直しが必要になることも
「気づけば当たり前になっていた疲れ」ほど、しっかり向き合う必要があります。
まとめ&行動プラン
脳疲労は目に見えないぶん、軽視されやすい問題です。
しかし、放っておけば集中力や判断力が落ちるだけでなく、心の不調にもつながりかねません。
まずは自分の状態に気づき、小さな改善から始めることが何よりも大切です。
【今日からできる行動プラン3ステップ】
- ひとつでいいから回復法を実践する
(入浴・深呼吸・ウォーキングなど、自分に合う方法から) - 睡眠・食事・スマホ時間を少しだけ整える
(すべて完璧を目指す必要はありません) - 不足する栄養はサプリで補う
→ 医師監修の「Rimenba」なら、1日4粒でDHA・イチョウ葉・ビタミンB群をまとめて補給可能
まずは一度試してみてはいかがでしょうか?