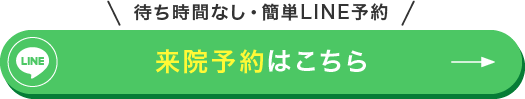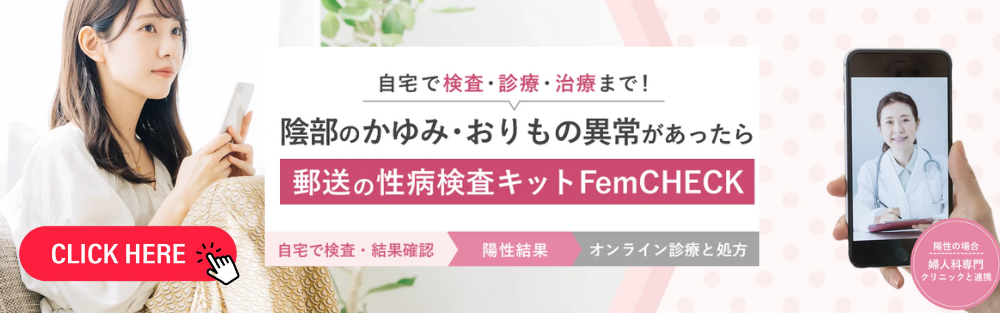予期せぬ妊娠に「中絶手術はいつまでできるの?」「費用はどのくらいかかるの?」と、誰にも相談できず一人でスマートフォンを握りしめていませんか?
中絶手術は、母体保護法で「妊娠21週6日まで」という明確な期限が定められています。そして、妊娠12週を境に手術の方法や心身への負担、費用は大きく変わります。
この記事では、産婦人科専門医が、
- 中絶が可能な正確な期間
- 妊娠週数による手術の具体的な違い
- 費用やリスクに関する正しい知識
- 万が一期間が過ぎてしまった場合の対処法
など、あなたの不安に一つひとつ答えながら、丁寧に解説します。知識を得ることで、少しだけ冷静になれるはずです。まずは、正しい情報を知ることから始めましょう。
中絶手術ができる週数は「妊娠21週6日目」まで
中絶手術ができる週数は「妊娠21週6日目」までです。手術をするかどうか悩んでいる方は「妊娠21週6日目」までに中絶手術を受ける必要があります。
母体保護法で「妊娠22週未満でなければならない」と定められており、いかなる理由があっても、この期間を過ぎると手術を実施できません。
いつでも受けられるわけではないことを、覚えておきましょう。
「私は今、何週目?」妊娠週数の正しい数え方
「妊娠21週6日目まで」という期限を知り、「自分の正確な妊娠週数が分からない!」と不安に思われたかもしれません。
妊娠週数の計算には主に2つの方法がありますが、ご自身での計算と、クリニックで診断する正確な週数にはズレが生じることが多いため注意が必要です。
| ご自身での計算(最終月経日から) | クリニックでの診断(超音波検査) | |
|---|---|---|
| メリット | 生理日さえ分かれば目安がわかる | 正確性が非常に高い |
| デメリット | 生理不順の場合、大きなズレが生じる | クリニックでの診察が必要 |
最終月経日から計算する方法(あくまで目安)
ご自身で計算する場合、「最後に生理が始まった日」を妊娠0週0日とします。市販の妊娠検査薬で陽性反応が出始めるのは、一般的に妊娠5週目頃からです。
ただし、この方法は生理周期が安定していることが前提です。もともと生理不順の方は排卵の時期がずれるため、あくまで目安と考えましょう。
超音波(エコー)検査で算出する方法(より正確)
クリニックでは、超音波(エコー)検査でCRL(赤ちゃんの頭からおしりまでの長さ)を測定し、最も正確な妊娠週数を算出します。
特に、胎児の大きさの個人差がほとんどない妊娠8~11週の時期の測定は、最も誤差が少ないとされています。

ご自身で計算した週数と、実際の週数がずれているケースは少なくありません。特に生理不順の方は注意が必要です。「まだ大丈夫」と思っていたら、実は中期中絶の時期に入っていた、ということも起こりえます。
ご自身の思い込みで判断せず、まずは一度クリニックを受診し、正確な週数を把握することが、あなたにとって最善の選択をするための最も大切な第一歩です。
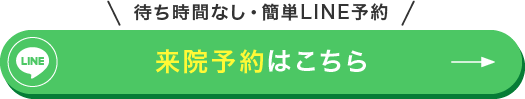
妊娠週数ごとの中絶手術の種類

妊娠週数によって「初期中絶」と「中期中絶」に分かれており、それぞれ手術方法や手続きなどが異なります。ここでは妊娠週数ごとの中絶手術の種類を詳しく解説していきましょう。
| 項目 | 初期中絶 (妊娠12週未満) | 中期中絶 (妊娠12週以降) |
|---|---|---|
| 手術方法 | 吸引法・掻爬法 | 人工的な陣痛誘発(出産形式) |
| 当院の術式 | 子宮に優しい手動真空吸引法(MVA) | 当院では非対応 |
| 心身への負担 | 比較的少ない(日帰り可能) | 大きい(数日間の入院が必要) |
| 痛み | 静脈麻酔で眠っている間に終了 | 陣痛や術前処置に伴う強い痛み |
| 必要な手続き | 不要 | 死産届の提出・火葬が必須 |
| 費用 | 10~15万円程度 | 40~60万円程度(公的補助あり) |
| 精神的負担 | 比較的少ない | 大きい |

妊娠12週の壁は、身体的・精神的・費用的、すべての面で非常に大きいのが現実です。だからこそ、私たちは「もし悩んでいるのなら、少しでも早い段階でご相談いただきたい」と強く願っています。決断を急かすためではなく、あなたにとって最善の選択肢を一緒に考える時間を確保するためです。
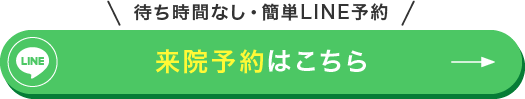
初期中絶(妊娠12週未満)
初期中絶とは、妊娠12週未満(妊娠11週6日目)の中絶手術のことです。この段階での手術は短時間で終わるため、日帰り手術が可能です。
妊娠検査薬で陽性が出た場合、超音波検査を行い「胎のう」を確認します。胎のうとは胎児を包む袋のようなもので、妊娠4~5週目頃に確認できるのが一般的です。
中絶手術は妊娠初期の早い段階で受けた方が、母体への負担は少なくすみます。妊娠が進むとお腹の中で胎児が育って大きくなるため、手術時に体の負担も大きくなるのです。
初期中絶手術では、吸引法もしくは掻爬(そうは)法で行われます。また吸引法には自動吸引法(EVA)と手動真空吸引法(MVA)があり、それぞれに特徴があります。
- 自動吸引法(EVA)・・・金属製のカニューレを使用。一定の吸引力で自動的に処置を行います。
- 手動真空吸引法(MVA)・・・プラスチック製の柔軟なカニューレを使用。手動で吸引力を調整できるので、患者への負担が少なく精密で安全性が高い。
当クリニックは子宮に優しい手動真空吸引法(MVA)を採用しています。
中期中絶(妊娠12週以降)
中期中絶では人工的に陣痛を起こして、本来の出産と同じように胎児を取り出します。子宮頸管や子宮口を開くための術前処置が必要なので、体への負担が大きいです。
術前処置は個人差があるものの、強い痛みを伴います。また、子宮収縮財を使用して陣痛を起こすため、手術中にも痛みを感じることも。
初期中絶に対応している医療機関は多いですが、中期中絶手術に対応できる施設は限られているので事前に確認しましょう。
手術後には4~6日程度の入院が必要であり、中絶手術にかかる費用も初期中絶手術と比べて高額になります。
また、妊娠12週以降に中絶手術を実施する場合、「死産届の提出」と「火葬による埋葬」が義務付けられています。
胎児の埋葬許可証を発行してもらい、役所に死産届と死産証書を提出します。中期中絶手術は初期中絶手術と比べて精神的にも肉体的にも負担が大きいでしょう。
ルナレディースクリニックは初期中絶のみ対応

当クリニックでは、妊娠12週未満(妊娠11週6日目までの)の初期中絶のみ対応しています。妊娠12週以降の中期中絶は取り扱っていません。
妊娠12週目以降の中期中絶は、母体にかかる負担が肉体的にも精神的にも大きいです。適切な設備のある医療機関で、慎重に処置を行わなければ危険性が高い手術です。
中絶をご検討中の場合はお早めにご相談ください。
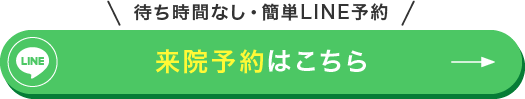
中絶を検討する際にクリニックを受診するタイミング
中絶を考えている方にとって重要なのは、「迷っている段階でも、まずは早めに受診する」ことです。妊娠しているかどうかを自己判断で放置すると、気づいたときには週数が進み、身体的・精神的負担が大きい中期中絶しか選べなくなる場合もあります。
受診のタイミングを先送りにしやすいケースとしては、
- 生理が数週間遅れているのに検査をしていない
- 出産か中絶かを決めかねている
- 相談できる相手がいないまま不安を抱えている
こうした状況に心当たりがある場合、受診するだけで「妊娠していない」とわかることもあります。逆に妊娠が確認された場合でも、早めに週数を正確に知ることで、より多くの選択肢を持つことができます。
受診は「中絶を決めた後にするもの」ではなく、「迷っているときにこそ必要な行動」です。
中絶手術ができる期間を過ぎた時の対処法

中絶手術ができる期間は妊娠22週未満(妊娠21週6日目まで)です。この期間を過ぎた場合、いかなる理由があっても中絶手術は禁止されています。
母体保護法が定めている期間を超えて中絶手術を行った場合、手術を執刀した医師と、手術を受けた患者は罪に問われます。
その場合、法律上は『出産する』という選択肢と向き合うことになります。しかし、金銭的な理由や家庭環境など、さまざまな事情で赤ちゃんを育てられない人もいるでしょう。
どうしても赤ちゃんを育てることができない場合には、里親制度や特別養子縁組制度といった制度を利用できます。1人で抱え込まずに誰かに相談してみましょう。
中絶手術ができる期間を過ぎた時の対処法
人工中絶手術ができるのは妊娠21週6日目までと法律(母体保護法)で定められています。妊娠22週以降になると、どのような理由であっても中絶手術は行えません。
医学の進歩により妊娠22週からは赤ちゃんが母体の外でも生きられる可能性があるとされているためです。妊娠22週以降の出産は「早産」として扱われ、新生児医療の対象になります。つまり、赤ちゃんの生命を尊重する倫理的観点と、母体に大きなリスクが伴う医学的観点の両面から、この週数が法律で定められているのです。
この期間を過ぎて中絶を行った場合、執刀した医師や患者本人が法的責任を問われることになります。そのため、妊娠22週以降は法律上『出産する』という選択肢しか残されません。
しかし、経済的な理由や家庭環境などで子どもを育てることが難しい方もいます。その場合は、里親制度や特別養子縁組制度といった公的な制度を利用する方法があります。決して一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談してみましょう。
中絶手術に関するよくある質問
最後に中絶手術に関するよくある質問をまとめました。
中絶手術の費用はどのくらいですか?
中絶手術にかかる費用は、妊娠週数によって異なります。妊娠12週未満の初期中絶と、妊娠12週以降の中期中絶では費用に差があります。
| 初期中絶 (吸引法・掻爬法) | 中期中絶 (陣痛促進剤) | |
| 初診料(問診・エコー検査など) | 1万円 | 1万円 |
| 術前検査(感染症検査など) | 1万円 | 1万円 |
| 手術(入院費・、埋葬費を含む) | 7〜10万円 | 40〜60万円 |
受診する際には各医療機関の費用を必ず確認してください
中期中絶は入院も必要になるため、初期中絶と比べて手術費用が高額です。人工中絶手術にかかる費用に関してはこちらの記事を参考にしてください。
関連記事:人工中絶手術にかかる費用や全体の流れ・注意点を解説!
一度中絶すると妊娠しにくいって本当ですか?
一度中絶したからと言って妊娠しにくくなるという事実はありません。
中絶回数と不妊リスクの関係に関しては、科学的な根拠が明らかになっていないため不安を感じる必要はないでしょう。むしろ、中絶手術後は妊娠する確率が高まる傾向にあります。
中絶すると妊娠しにくくなるのかについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:一度中絶すると妊娠しにくい?後遺症や中絶履歴が残るか解説
中絶手術は何週から受けられる?
「中絶はいつからできるの?」と気になる方も多いでしょう。一般的に、妊娠が成立していることが医学的に確認できてからでなければ、中絶手術を受けることはできません。
そのための条件としては、
- 妊娠検査薬で陽性反応が確認できること(妊娠4週以降が目安)
- 超音波検査で胎嚢(たいのう)が確認できること
- 子宮外妊娠などの異常妊娠が起きていないこと
これらの条件を満たしたうえで、医師が安全と判断した場合に手術を受けられます。実際に多くのクリニックでは妊娠5週以降から手術の実施が可能とされています。
ただし、妊娠週数が早すぎると胎嚢がまだ確認できない場合があるため、手術を急がず妊娠6〜9週ごろに手術を勧められるケースもあります。これは子宮や胎嚢の状態を見極め、安全に処置するためです。
「できるだけ早く受けたい」と思っても、医学的に必要な条件が整わなければ手術は行えません。まずはクリニックで検査を受け、医師に適切な時期を確認しましょう。
まとめ

中絶手術はタイミングに注意する必要があります。中絶手術を後回しにしてしまうと、中絶できる期間が過ぎてしまう可能性があります。
中絶には手術が可能な期間が決められており、いつでもできるという訳ではありません。
中絶手術ができる期間は法律によって定められており、妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)です。
この期間を過ぎてしまうと人工妊娠中絶手術はできないため、出産するしか方法はありません。中絶手術ができる期間がいつまでかをきちんと把握して、手術を受けるかどうかをできるだけ早めに決めましょう。
中絶手術は妊娠初期に行った方が負担が軽いです。中絶を検討している方は身近な人や医師などに相談してみましょう。