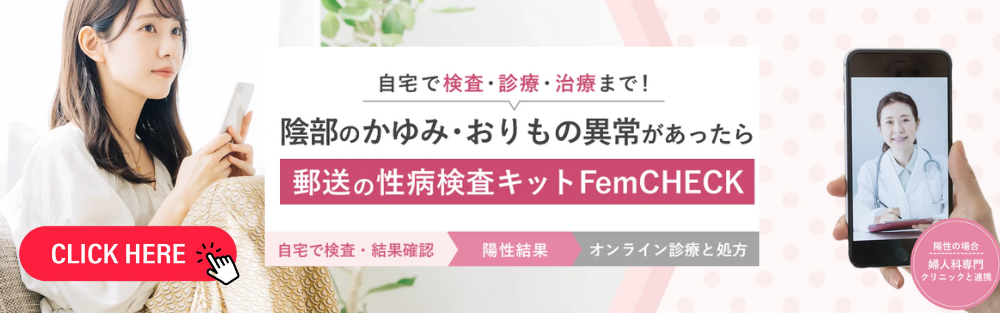「最近、目が疲れやすい…」「視界がぼやける時がある」
実は、40代以降の男女の多くが気づかぬうちに「眼圧の上昇リスク」を抱えています。
眼圧とは、眼球内の圧力のこと。これが高くなると、視神経にダメージを与え、最悪の場合「緑内障(失明リスク)」につながることもあります。だからこそ、早い段階からの対策が重要です。
本記事では、眼圧を下げる作用が期待される栄養素や食材、そして食事で不足しがちな成分を補える注目のサプリメント「Eyepa(アイーパ)」までを網羅的にご紹介。医師監修・GMP打錠・無添加処方で話題のEyepaは、日々の食事と合わせて摂取することで、より効果的に「ひとみの健康維持」をサポートします。
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、始めどきです。
あなたの未来の視界を守る一歩、ここから踏み出してみませんか?
眼圧と緑内障の基礎知識

視力の低下やぼやけ——その原因のひとつが「眼圧の異常」です。
ここでは、眼圧の定義や正常値、さらに放置すると失明につながるリスクがある「緑内障」について、正しい知識を整理します。
眼圧とは?正常値と測定方法
眼圧とは、「眼球の中にかかっている圧力」のことを指します。眼の中では、房水(ぼうすい)と呼ばれる透明な液体が常に循環しており、この房水の生成と排出のバランスによって眼圧は保たれています。
- 正常な眼圧の目安は、10〜21mmHg(水銀柱ミリメートル)。
- 測定には、非接触型(空気圧)やアプラネーション型(直接角膜に接触する方式)のトノメーターが使用されます。
眼圧がこの範囲を超えて高くなると、視神経に負荷がかかりやすくなり、緑内障などの病気のリスクが高まるとされています。
緑内障の有病率とリスク
緑内障は、視神経が徐々に傷ついていき、視野が狭くなる病気です。特徴的なのは、「初期症状がほとんどないまま進行する」という点で、気づいたときにはかなり進行しているケースも少なくありません。
実際、日本人の40歳以上の約5%(20人に1人)が緑内障に罹患しているとされ、早期発見・早期ケアの重要性が年々高まっています。
さらに、日本眼科学会の疫学データによって、緑内障のリスク因子として以下の項目が確認されています。
- 高眼圧
- 加齢(特に40歳以上で発症率が上昇)
- 近視(高い近視の人ほどリスクが数倍)
- 家族歴(血縁者に緑内障患者がいる場合)
- 糖尿病・高血圧などの全身疾患
これらのデータから、40歳以上の方を中心に、緑内障の早期発見と定期的な眼検査の重要性が非常に高いことが裏付けられています。
眼圧が上がる仕組み
そもそも、眼圧はなぜ上がるのでしょうか?答えは、「房水の出口が詰まり、排出がスムーズに行われなくなる」からです。
房水は毛様体で作られ、シュレム管という排出口から眼外へと排出されます。しかし、この出口が狭くなったり、機能が低下したりすると、眼球内に房水がたまり、眼圧が上昇してしまうのです。
加えて、以下のような日常的な要因も、眼圧上昇に影響すると言われています。
- 長時間のスマホ・PC使用による姿勢の悪化(前傾)
- 血糖値の乱高下(糖尿病との関連)
- ストレスや睡眠不足
特に「寝ながらスマホ」などの習慣は、眼圧上昇を引き起こすとされており、生活習慣の見直しも重要なケアのひとつです。
眼圧を下げる栄養素と食べ物7選

眼圧のコントロールには、日々の「食べ方」が大きく関わっています。
ここでは、視神経や房水(ぼうすい)の流れに良いとされる栄養素と、それを含む身近な食材を7つ厳選してご紹介します。
ルテイン(緑黄色野菜)
ルテインは、眼の黄斑部(視力の中心)に多く存在し、青色光や酸化ストレスから網膜を守る抗酸化成分です。
体内で合成できないため、食事またはサプリでの摂取が必須です。
- 推奨摂取量:1日あたり6mg以上(米国NIH基準)
- 含有量の多い食材:ケール(100gあたり21.9mg)、ほうれん草(100gあたり11mg)など
- 実践ヒント:油と一緒に摂ると吸収率UP。オリーブオイル炒めがおすすめ。
アントシアニン(ベリー類)
アントシアニンは、ベリー類の紫色の色素成分で、血流改善と眼圧の低下に関与することで知られています。
- 1日目安量:40~90mg
- 食材例:ビルベリー、ブルーベリー、ブラックベリー
- 実践ヒント:ヨーグルトやグラノーラと一緒に朝食に。
オメガ‑3脂肪酸(青魚)
DHA・EPAは、視神経の膜を構成し、神経保護・抗炎症作用を持つ重要な脂肪酸です。房水の排出路(シュレム管)の柔軟性を高めることで、眼圧低下作用が期待されます。
- 摂取目安:DHA+EPA 合計1,000mg/日
- 食材例:サバ、イワシ、サンマ、サーモンなど
- 実践ヒント:手軽な「サバ缶」なら1日1缶でOK。味噌煮・水煮でレシピも広がります。
ビタミンA・C・E(抗酸化)
これらのビタミンは「抗酸化ビタミン」として知られ、視神経の酸化ストレスを緩和する働きがあります。
- A:網膜の光受容体を正常に保つ(レバー、うなぎ、にんじん)
- C:眼球の水晶体を保護し、抗酸化(キウイ、パプリカ、ブロッコリー)
- E:血行促進と抗炎症(アーモンド、アボカド)
- 実践ヒント:炒め物にアボカド油+パプリカ+ブロッコリーで一品完成。
ビタミンB群・葉酸
血流を促進し、神経伝達や代謝に関与するのがビタミンB群。特に葉酸・B6・B12は、ホモシステインという血管ダメージ因子を下げることで、視神経保護に貢献します。
- 摂取例:玄米、レバー、卵、ほうれん草
- 葉酸目安:240μg/日(妊婦以外の成人基準)
- 実践ヒント:「玄米おにぎり+ゆで卵+みそ汁+ほうれん草おひたし」でパーフェクト定食。
アスタキサンチン(甲殻類)
アスタキサンチンは、ビタミンEの約6,000倍とされる超抗酸化成分。眼球の毛細血管を守り、視力維持に効果があるとされます。
- 含有食材:サーモン、エビ、カニ、イクラ
- 目安量:1日2〜4mg程度
- 実践ヒント:サーモンとほうれん草のバターソテーなど、ルテインとの相乗効果も。
亜鉛・ペンタデシルなど補助成分
目の粘膜を守る「亜鉛」や、涙液を安定させる「ペンタデシル」などの補助成分も重要です。
特にデジタルデバイスを長時間使用する方にとっては、乾き目対策にも有効です。
- 食材例:カキ、牛肉、カボチャの種、Eyepaサプリメントなど
- 実践ヒント:Eyepaなら10種以上の有効成分が1日2粒で完結。
避けるべき食べ物・生活習慣

眼圧を上げるのは、病気だけではありません。実は、私たちが日常的に口にしている飲み物や、何気ない生活習慣の中にも、眼圧を一時的・慢性的に上昇させる要因が潜んでいます。
ここでは、特に注意すべき3つの代表例をご紹介します。
カフェインの過剰摂取
コーヒーやエナジードリンクに含まれるカフェインは、覚醒作用や血管収縮作用を持ちます。近年の研究では、カフェイン200mg(コーヒー2杯相当)を摂取後に眼圧が上昇するという報告があり、特に高眼圧症や緑内障のリスクを抱える人には注意が必要です。
- W日本人の摂取基準は、1日あたり400mg未満が目安とされていますが、個人差も大きいため「コーヒーは1日1〜2杯まで」を意識するとよいでしょう。
- エナジードリンクや濃いめの紅茶、抹茶ラテなどにも含まれるため、累積量に注意が必要です。
代替策
- デカフェ(カフェインレス)コーヒーやルイボスティー、麦茶などを活用。
- 朝は温かい白湯、午後はノンカフェインのハーブティーなどでリズムを整えるのもおすすめです。
高糖質・高脂肪食
「血糖値の乱高下」は眼圧にも悪影響を与えます。特に、HbA1c(平均血糖値)の高値は高眼圧と関連するという報告もあり、糖質中心の食生活はリスク因子といえます。
また、飽和脂肪酸を多く含む食事(揚げ物、加工肉、クリーム系の食品など)は、血流を悪化させることで房水の循環にも影響を与える可能性があります。
代替策
- GI値(血糖値上昇の指標)の低い食材を中心に摂る(例:玄米、雑穀、納豆など)
- 脂質はオメガ3(青魚・アマニ油)を意識し、飽和脂肪酸を控える
ポイント
- 「糖質×脂質」のセット食(菓子パン+コーヒー、ラーメン+チャーハン)は眼圧にも悪影響。
スマホ・PCの長時間使用
デジタルデバイスによる眼精疲労や姿勢の悪化も、眼圧上昇の一因とされています。
- スマホやPCを前傾姿勢で長時間見続けると、首肩の圧迫→血流悪化→眼球への圧力上昇に繋がります。
- 特に「寝る前のスマホ(寝スマホ)」は、暗所+仰向け姿勢+ブルーライト刺激の3重リスクにより、眼圧を大きく押し上げる要因となります。
代替策
- 30分作業ごとに1回、目線を遠くに移してピント調節(いわゆる「20-20-20ルール」)
- 就寝前1時間はスマホやPCを避け、読書や音楽などの“脱ブルーライト”時間を意識
栄養ギャップを埋めるサプリメント活用術

食事だけで、目に必要な栄養素を毎日まかなうことはできるのか?答えは、「非常に難しい」というのが現実です。
ここでは、栄養摂取の現状と、サプリメント活用の合理性について、エビデンスをもとに解説します。
食事だけでは足りない現実
ルテイン・アントシアニン・オメガ3脂肪酸など、目の健康維持に役立つ栄養素は数多くありますが、実はどれも体内で合成できないか、あるいは短時間で排出されてしまう性質を持っています。
特に注目されているのが、ルテインの摂取量のギャップです。
- 推奨摂取量:6mg/日以上
- 一般人の平均摂取量:約1.5mg/日
このように、食生活が整っている人ですら約1/4しか摂れていないのが実情です。また、アントシアニン(ビルベリーなど)は体内で24時間以内に排出されるため、「毎日補う」ことが必須です。
さらに、スマホ・PCの使用によって眼の酷使が進んでいる現代では、こうした成分を“継続的かつ安定して”摂取できる手段が必要です。
サプリ選び5つのチェックポイント
サプリメントを選ぶ際は、「なんとなく良さそう」ではなく、以下のような5つの視点で信頼性を見極めることが大切です。
- 配合量が明記されているか
ルテイン16mg、ビルベリー264mgなど、目安摂取量を満たしているか確認。 - 原料や製造工程が明らかか
GMP認証工場で製造されているか、原産地・抽出法は公開されているか。 - 医師・専門家の監修があるか
医学的根拠や臨床データに基づいているか。第三者評価があるか。 - 返金保証・サポート体制が整っているか
継続しやすさを考慮して、定期縛りの有無やサポート窓口を確認。 - 添加物の有無・飲みやすさ
香料・保存料などが不要な添加物として使われていないか。粒の大きさや味も継続に影響します。
これらの基準をすべて満たすアイテムは、実はそう多くはありませんが、次項で紹介する「Eyepa(アイーパ)」は、その希少なサプリメントのひとつです。
Eyepaの成分設計とエビデンス
「Eyepa(アイーパ)」は、10種以上の有効成分を「1日2粒」に凝縮した、ひとみのためのオールインワンサプリです。
特長①:業界最高水準の成分配合
- ビルベリー(アントシアニン):264mg
- ルテイン:16mg
- ゼアキサンチン:16mg
- アスタキサンチン:3.2mg
- ビタミンA/C/E、亜鉛、ペンタデシルなども網羅
これらを個別に摂取するとコストも手間も増大しますが、Eyepaならたった2粒で完結します。
特長②:信頼性の高い製造と監修体制
- 原材料について眼科専門医監修
- GMP認証国内工場で打錠、品質管理を徹底
- 無添加(保存料・香料・甘味料なし)設計で安心して毎日続けられる
特長③:始めやすい価格と安心保証
- 初回特別価格:4,378円(税込)
- 15日間返金保証(クレカ決済限定)
- 定期縛りなし
このように、Eyepaは成分・信頼性・継続性のすべてを兼ね備えた設計になっています。
眼圧を下げる生活習慣3ステップ

食事の工夫とあわせて取り組みたいのが、「生活習慣の見直し」です。眼圧は、一日の中でも姿勢や血流、睡眠の質などによって変動します。
ここでは、日常生活で無理なく続けられる3つの生活習慣をステップ形式でご紹介します。
有酸素運動
もっとも効果が報告されているのが、「有酸素運動による眼圧の低下」です。
ウォーキング・ジョギング・水泳・自転車などを週3回・30分以上実施することで、眼圧を2〜5mmHg下げる効果が複数の研究で認められています。
- 軽めの運動(ウォーキング)でも十分に効果があり、特に運動後1〜2時間以内に眼圧が下がる傾向が明確です。
- 高強度の運動(インターバルトレーニングなど)では、さらに眼圧低下効果が顕著との報告もあります。
実践ヒント
- ラジオを聞きながらの散歩、駅の1区間を歩くなど、日常生活に「移動運動」を取り入れると無理なく継続できます。
姿勢・睡眠環境の最適化
姿勢や睡眠の質も、眼圧の上昇に大きく関係しています。特に就寝時の「寝姿勢」や、前屈みの読書・スマホ使用などが問題視されています。
- うつ伏せ寝や寝スマホは、眼球への物理的圧力や血流滞留によって眼圧を上げる要因に。
- 枕が高すぎると頸動脈が圧迫され、視神経への血流が悪化する可能性があります。
- 照明が暗すぎる環境では瞳孔が開き、眼内圧が上がるリスクもあります。
改善のポイント
- 仰向けで寝る/スマホは就寝1時間前までに
- 枕の高さは4〜6cmが推奨目安
- 読書灯は200lx以上の照度を目安に
定期検診とセルフチェック
眼圧や視野の異常は、自覚症状が出にくいため、年1回の眼底検査と眼圧測定を受けることが早期発見のカギになります。
- 眼科での検査項目:眼圧測定/視野検査/眼底カメラなど
- 家庭用トノメーター(眼圧計)を使って、自分で定期的にチェックすることも可能です。
眼圧測定は保険適用の一般診療で受けられるため、費用面の負担も少なく、気軽に受診できます。
セルフケアのすすめ
- 家族に緑内障の人がいる場合は40歳前後から検診を
- 朝と夜で眼圧は変動するため、測定時間を固定して記録するのがおすすめ
まとめ:今日からできる5ステップ眼圧ケア
眼圧は、自覚症状がないまま進行する“サイレントトラブル”です。だからこそ、日常生活に無理なく取り入れられる習慣を「今から始める」ことが大切です。
ここでは、これまでご紹介した内容をふまえ、誰でも今日から実践できる5つのステップをまとめました。
行動リスト(食材・運動・休息)
- 毎日の食事に「5色の野菜+青魚」を1品ずつ加える
・緑(ほうれん草)/赤(パプリカ)/紫(ブルーベリー)など色を意識するだけでも、自然と抗酸化
・血流サポートに役立ちます。
・サバ缶1個+ルテイン配合の野菜炒めでもOK。 - 週150分の有酸素運動(30分×週5日)を目安にする
・ウォーキング・軽いランニング・サイクリングなど。
・運動後1〜2時間は眼圧が自然に下がる“ゴールデンタイム” - 枕の高さ・寝室の明るさを整える
・枕は4〜6cm、寝室は200lx以下の落ち着いた照明がおすすめ。
・「寝スマホ」は今夜からやめてみましょう。 - 水分補給・姿勢・休憩のルールを習慣化
・こまめな水分補給、30分に一度の「20-20-20ルール(20秒、20フィート先を見つめる)」を取り入れると、目の緊張が和らぎます。 - 年1回の眼科検診を必ず受ける
・40歳以上、または家族に緑内障経験者がいる方は特に重要。
・「何もなかった」と確認するだけでも大きな一歩です。
Eyepaを取り入れる次の一歩
ルテイン、ビルベリー、ゼアキサンチン、アスタキサンチンなど、必要な成分を毎日バランスよく・手軽に補いたいなら、Eyepa(アイーパ)の活用が非常におすすめです。
Eyepaの特長
- 1日2粒で10種類以上の有効成分をまとめて摂取
- 眼科医監修・GMP認証工場打錠・無添加設計で安心
- 初回50%OFF(税込4,378円)+15日間返金保証つき(クレカ限定)
- 定期購入の縛りなし
「毎日の習慣」として無理なく続けられるEyepaは、
「まだ病院に行くほどではないけど、将来のために何か始めたい」
というあなたに、ぴったりの第一歩です。