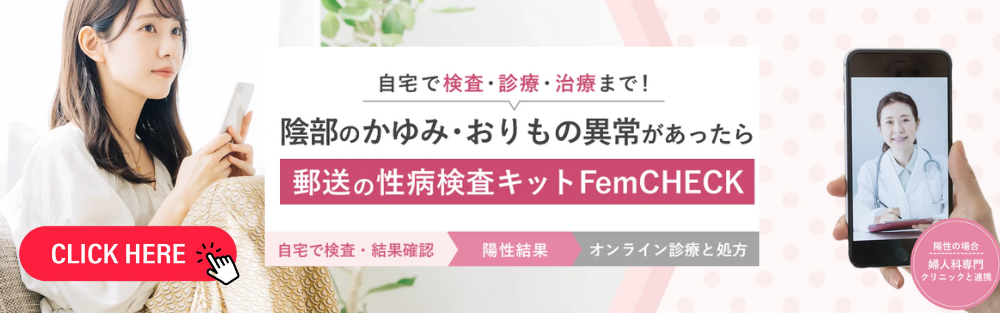「最近、物忘れが増えたかも…」
そんな不安を感じたあなたへ。40代からの“脳のメンテナンス”は、人生100年時代を生き抜くカギです。
脳活とは、認知機能の維持や低下予防を目的とした習慣のこと。ゲームや体操、栄養管理まで、その方法はさまざまです。
本記事では、脳活の基本から毎日続けられる実践法、さらにサポートアイテムとして注目されている知力健康サプリ「Rimenba(リメンバ)」まで、わかりやすくご紹介します。
脳活が必要とされる背景—統計でわかる認知症リスク

超高齢社会が進行する日本。「認知症」が目に見える影響を及ぼす未来が、もうすぐそこに迫っています。
政府研究チーム(九州大学・二宮教授ら)による推計では、認知症高齢者数は2022年の約443万人から、2030年には約523万人、さらに2040年には約584万人にまで増加すると予測されています。
加えて、65歳以上人口に占める認知症の有病率も、2022年の12.3%→2030年には14.2%→2040年には14.9%と着実に上昇傾向にあります。予備軍とも言える軽度認知障害(MCI)も2030年には約593万人に達し、高齢者の約3〜4人に1人が何らかの認知機能低下を抱える構造に。これはもはや“他人事”ではありません。
2030年・2040年の将来推計から見える認知症の“今”
- 2022年:約443万人(有病率12.3%)
- 2030年:約523万人(有病率14.2%)
- 2040年:約584万人(有病率14.9%)
政府統計では、高齢化の進行に伴い、認知症人口が2030年までに80万人、2040年までにさらに140万人増えると予測されており、この傾向は今後も継続すると見られます。
背景には、団塊世代が2025年以降に75歳以上へ達するという人口構造の急激な変化があり、医療・介護へのニーズも同時に高まる“社会構造的変化”が進行中です。こうした流れは、まさに「認知機能維持=国民レベルの課題」として迫っていると言えるでしょう。
“軽度認知障害(MCI)”を含めた広い危機感
- 2022年時点のMCI人口:約558万人(有病率15.5%)
- 2030年には約593万人、2040年には約613万人に増加すると推計
つまり、MCIと認知症を合わせると、将来的には高齢者の約3〜4人に1人が“脳の健康”に何らかのリスクを抱えるということになります。このような現状から、脳活は「認知症になってから」ではなく、MCIの段階、あるいは健康な今のうちから取り組むべき「予防策」としての意味合いが非常に強いのです。
だからこそ、日常生活に無理なく取り入れられる「脳活習慣」が求められています。
メディアに見る「脳活ブーム」とシニアライフスタイル
こうした背景を受け、メディアやアプリの領域でも「脳活」人気が高まっています。
- 西日本新聞社が発行する「脳活新聞」の公式発表によれば、2025年3月にウェブ会員数が1万2000人を突破。これを記念したプレゼントキャンペーンも実施され、シニア層の関心の強さが裏付けられています。
- 日本経済新聞社が提供する「日経脳活クイズ」アプリは、App Store上でレビュー件数1.6万件、平均評価4.4(カテゴリ「雑誌/新聞」第12位)という高評価を記録。スマホで楽しめる間違い探しやクロスワードをきっかけに、ダウンロード数は数万件規模に達していると見られています。
今日から取り組める脳活3ステップ

「頭を使う」「体を動かす」「食を整える」、この3本柱を日常に取り入れることが、脳活を習慣化するための最短ルートです。それぞれのステップを具体的にご紹介します。
①「頭を使う」:スマホアプリ&クイズで毎日15分
スマホアプリを活用すれば、毎日15分で手軽に「脳に軽い負荷」をかけることができます。
たとえば、日本でも親しまれているLumosityは、世界中で1億人以上が利用する脳トレアプリで、App Storeには評価星3.9・レビュー523件の記録があります(App Store「Lumosity: 毎日の脳トレゲーム」ページ)。
Lumosityの提供先Scienceページでは、「10週間トレーニングを継続した結果、作業記憶や処理速度で統計的に有意な改善」が認められたと報告されており、科学的根拠も備えています
さらに、日常の習慣として「毎日15分」というハードルを低く設定することで、継続しやすく習慣化にもつながります。「頭を使う」第一歩として最適です。
②「体を動かす」:コグニサイズと脳活体操
国立長寿医療研究センターが提唱するコグニサイズは、運動と認知課題を同時に行い、脳と体を同時に刺激できる運動法です。
- 「足踏みしながらしりとり」や「ステップと数字カウント」を組み合わせる中強度エクササイズで、認知機能の低下抑制が研究で示されています。
- 神奈川県の公式資料でも、地域高齢者向けに「足踏み+手拍子」などを組み合わせた具体メニューを普及し、介護予防として推奨しています。
10〜15分の短時間ながら、継続性と効果のバランスが取れたプログラムです。
③「食を整える」:地中海食・MIND食の実践ポイント
日々の食事に「地中海食」や「MIND食」(「地中海食」と「DASH食(高血圧予防食)」の要素を組み合わせた認知症予防に特化した食事法)を取り入れることで、認知症リスクの低減が期待されます。
- WHOのガイドラインでは、地中海食を順守することで軽度認知障害やアルツハイマー型認知症のリスク低下が示されており、魚・オリーブオイル・ナッツの摂取との関連が強いと報告されています。
- 2015年の研究では、MIND食が「年齢における認知機能低下を平均約7.5年分遅らせる」という結果が得られるなど、食による予防効果が数値で確認されています。
普段の和食に「オリーブオイルをちょい足し」「魚・ナッツを毎食ひとつまみ多めに」するだけでも、実践できるでしょう。
ちなみに、MIND食の基本的な構成は以下のとおりです。
積極的に摂取したい食品
- 緑黄色野菜(特に葉物)
- ナッツ類
- ベリー類(ブルーベリーなど)
- 全粒穀物
- オリーブオイル
- 魚、鶏肉、豆類、赤ワイン(適量)
避けるべき食品
- バター/マーガリン
- 赤身肉
- 揚げ物/ファストフード
- チーズ
- お菓子類(加糖食品)
足りない栄養を補うサプリメント活用術

「食事からすべての栄養をまかなう」のは難しいものです。特に葉酸・ビタミンB群は、脳の健康維持に重要ながら、日常の食事だけでは十分な摂取が期待できません。
ここでは、「不足しがちな栄養を補う意義」と「サプリを選ぶ基準」を整理します。
葉酸・ビタミンB群が「脳のホモシステイン」を抑えるメカニズム
葉酸やビタミンB6・B12は、ホモシステインの代謝に関わり、血中のホモシステイン濃度を下げる作用があります。ホモシステインが高いと脳血管にダメージを与え、認知機能の低下リスクが増加することが知られています。
- 高齢者818名を対象とした二重盲検試験では、葉酸800μg/日を3年間摂取した群で、認知機能改善とホモシステイン低下が確認されました。
- また、葉酸・B6・B12を組み合わせて摂取すると、ホモシステインが有意に低下する結果が得られ、さらにMCI(軽度認知障害)患者の脳萎縮速度が鈍化したとの報告もあります。
これらの知見から、“ホモシステインを下げる”ことが脳のヘルスケアにおけるサプリ活用の科学的根拠となっているのです。
サプリ選び5つのチェックポイント(配合量・GMP・医師監修ほか)
サプリメントは手軽ですが、安心して選ぶには以下の着眼点が欠かせません。
◆配合量が目安摂取量を満たしているか
葉酸400 µg・B6・B12の目安を確認し、パッケージや公式サイトに含有量が明記されている製品を選びましょう。
<サプリの配合設計で重視すべき目安値>
| 栄養素 | 成人推奨量 | 製品設計の目安配合量 |
|---|---|---|
| 葉酸 | 240 μg/日 | 240~400 μg |
| ビタミンB6 | 1.2~1.5 mg/日 | 1.2~2 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg/日 | 2.4 μg以上 |
◆GMP認定工場で製造されているか
GMPは「適正製造規範」の略。製造工程における品質保証の目安で、安全・衛生面に優れた製品を選ぶ際の重要な指標です。
◆医師監修や栄養学的エビデンスがあるか
製品が専門家の監修を経ているか、機能性表示食品やトクホの認定があるかを公式サイトでチェックしてください。
◆不要な添加物が少なく、原材料が明確か
着色料や香料の有無、原料の原産地・配合割合が明示されているかを確認しましょう。
◆継続しやすい価格と飲みやすい形状か
1日あたりのコストや粒サイズ、飲みやすさにも配慮。続けることが最大の効果につながるため、この点は軽視できません。
これらのポイントを押さえることで、自分に合ったサプリメントを見極める力が身につきます。「品質」「成分」「継続性」のバランスが取れた製品を選ぶことが、脳の健康を守る第一歩です。
そして、これらの条件をすべて満たした注目のサプリメントが「Rimenba(リメンバ)」です。次の章では、その成分設計・安全性・価格面を詳しく見ていきましょう。
Rimenbaの実力を徹底検証
脳活をサポートするサプリメントは数多く存在しますが、「医師監修」「品質の安全性」「継続しやすい設計」のすべてを兼ね備えた製品はそう多くありません。この章では、注目の脳活サプリ「Rimenba(リメンバ)」の実力を多角的に解説します。
医師監修の成分設計
Rimenbaは、脳の健康維持に注目される成分をバランスよく配合しています。
- 葉酸 240μg
- ビタミンB6/B12
- DHA・EPA(オメガ3系脂肪酸)
- プラズマローゲン(ホタテ由来)
なかでも、葉酸・ビタミンB群はホモシステイン代謝に関わり、血中ホモシステイン濃度を低減することで脳血管へのダメージを軽減する効果が期待されます。これは複数の臨床研究で実証されており、MMSE(認知機能検査)スコアの維持・改善にも寄与するとされているのです。
また、DHA・EPAは神経細胞膜の構成に関与し、プラズマローゲンは脳内での情報伝達における重要物質として近年注目されています。いずれも、「認知機能の予防・維持」にエビデンスが存在する成分です。
品質管理と安全性—GMP & 医師監修体制
Rimenbaは、品質管理においても万全の体制が取られています。
- 製造は、厚生労働省のGMP(適正製造規範)基準を満たした国内工場で行われており、製造過程の衛生管理や品質チェックが徹底されています。GMPとは、原料の受け入れから製造・出荷に至るまでの各工程を一貫して管理する制度で、厚労省によってその遵守が推奨されています
- Rimenbaの成分設計は脳神経内科医の監修のもとで開発されています。
- 香料・着色料・保存料・酸味料・甘味料・増粘安定剤といった不要な添加物を一切使用していない点も、毎日摂取するサプリメントとしての安心感につながります
このように、Rimenbaは「誰が作っているか」「どこで作っているか」「どのような設計思想で作られているか」という、サプリ選びにおける重要な基準をしっかりと満たしているのです。
続けやすい価格設計とサポート体制
継続が前提となるサプリメントにとって、「始めやすさ」と「続けやすさ」は極めて重要です。
Rimenbaは以下のようなユーザー配慮型のサービス設計がなされています。
- 初回50%OFF(4,298円)
- 15日間の返金保証制度(クレカ決済限定)
- 送料無料
- 定期コースの「縛りなし」(解約は次回発送10日前までOK)
「とりあえず試してみたい」「サポートのあるところから始めたい」という方にとって、Rimenbaは選びやすく、かつ安心して続けられるサプリメントといえるでしょう。
まとめ:今日から始める“脳活+Rimenba”ルーティン
近年、「脳の健康」は高齢期だけでなく、40代・50代の段階から取り組むべきテーマとして広がりを見せています。実際に、認知症の前段階であるMCI(軽度認知障害)は65歳以上の15%超が該当するとされ、予備軍も含めれば「高齢者の約3~4人に1人」が認知機能に不安を抱えている状況です。
このような現状を踏まえ、本記事では以下の3点を軸にお伝えしてきました。
■ 記事の要点まとめ
- 「脳活」とは、頭・体・食を通じて認知機能を鍛える習慣のこと
- 具体策としては「スマホアプリでの脳トレ」「コグニサイズ」「地中海食」が有効
- 食事だけでは補いにくい栄養素(葉酸・B群など)は、サプリでの補完も重要
- Rimenbaは、必要な栄養をワンストップで配合し、GMP製造・医師監修・無添加設計で安心
- 初回50%OFF・返金保証付き・定期縛りなしと、始めやすいサポート体制も充実
■ 明日からできる脳活+サプリ習慣チェックリスト
- スマホに脳トレアプリを1つ入れる
- 朝のウォーキングに「しりとり」や「暗算」を組み合わせてみる
- 昼食を「魚・オリーブオイル中心」にしてみる
- 栄養面の不安を感じたら、Rimenbaを1日4粒から試してみる
「脳活は、今日始めた人が一番得をする」——そう言っても過言ではありません。
気づいた今こそ、自分の未来のために一歩を踏み出すタイミングです。
まずは、Rimenba公式サイトで詳細をチェックしてみてください。