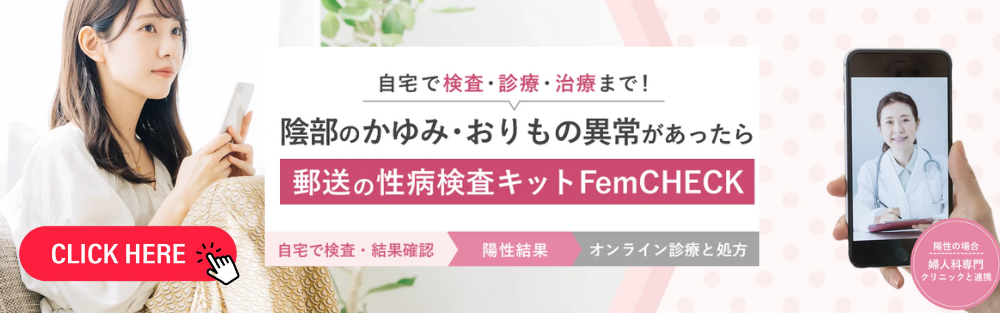「生理不順や避妊のために低用量ピルを飲んでみたいけど、副作用が心配」という声は多く、実際に「どんな症状が出るの?」「血栓症って怖い?」と不安を抱えている方も少なくありません。
本記事では、低用量ピルの副作用を中心に、起こりやすい症状やその対処法、服用時の注意点をわかりやすく解説します。正しい知識を身につけ、上手に付き合えば、低用量ピルは避妊だけでなく生理痛の緩和など多くのメリットが得られます。気になる方はぜひご一読ください。
低用量ピルに副作用はある?

低用量ピルは従来のピルに比べてホルモン量が少なく、副作用が軽減されているのが特徴です。しかし、「まったく副作用が起こらない」というわけではありません。吐き気や頭痛、下腹部の不快感など、初期に感じやすい症状もあります。
もっとも注意すべきは血栓症です。血栓症そのものの発症率は高くはありませんが、万が一発症すると重大な健康被害につながる恐れがあります。
なお、妊娠の可能性がある場合や血栓症の可能性がある場合など、医師の判断によりピルを一時中止するケースもあるので、定期的に診察を受けることが大切です。
低用量ピルにおける副作用の症状

低用量ピルにおける副作用の症状には、軽いものと重大なものがあります。重大なものの代表格が血栓症です。ここではそれぞれの副作用についてわかりやすくまとめました。
・吐き気や頭痛などの軽度の症状
・血栓症
・乳がんや子宮頸がんのリスク
軽度の症状
低用量ピルを初めて飲んだ場合、体が慣れるまでの1~2ヶ月は、吐き気や頭痛などの副作用を感じ、体がピルに慣れていくとともに、これらの症状は見られなくなる方が多いです。もちろん、まったく副作用を感じない方もいます。
主にみられるピルの軽い副作用は以下の通りとなっています。
・吐き気・下痢
・倦怠感
・頭痛
・胸の張り
・不正出血
血栓症
血栓症とは、足の静脈に血の塊ができる病気です。血の塊が血液の流れに乗って心臓から肺に到達すると、肺塞栓症という命に関わる重大な病気を引き起こします。基本的にはピルに含まれる卵胞ホルモンの量が多ければ多いほど、血栓症の発症率が上がるため、ピルの中でも低用量ピルは危険性がそれほど高くはないのですが、
乳がんや子宮頸がんのリスク
ピルの内服によってリスクが上がる病気は、血栓症だけではありません。乳がんや子宮頸がんについてもリスクが上昇する可能性があることがわかっています。
乳がんについては、ピルの内服で明らかにリスクが上がるという研究結果が複数報告されています。ただし、低用量ピルを内服している人については逆にリスクが下がるという報告も見られており、続報が待たれるところです。
上記より、現在乳がんをお持ちの方については、ピルは内服してはいけないということになっています。また乳がんを発症してから5年以上再発がない方については、ピルの投与を慎重に検討する必要があります。さらに乳がんは家族内発症が多いため、血のつながった方に乳がんの方がいる場合も慎重投与となっています。
子宮頸がんについては、ピル内服中のリスクは上がるものの、ピル中止後10年以上経過すると通常の方と同じくらいまでリスクが減るという報告もあります。
誤解されやすい低用量ピルの副作用

低用量ピルの副作用として誤解されているものには、以下のようなものがあります。これらは全て医学的な裏付けがないものです。ご心配な方は、ピルを処方してもらうときに担当医にお尋ねください。
・太る
・免疫力低下
・味覚が変わる
・貧血
・不妊
低用量ピルで副作用が起こる期間の目安

低用量ピルで副作用が起こる期間の目安は、服用を開始してから3ヶ月以内です。この時期は、身体がピルに慣れておらず、軽い副作用が起きやすくなっています。
ただし血栓症に関しては、飲んでいる期間に関係なくいつでも発症する可能性がありますので、注意が必要です。
血栓症について知っておきたいこと

低用量ピルの内服を始めるにあたり、血栓症について正しく知ることはとても大切です。ここでは、低用量ピルを飲むとどうして血栓ができやすくなるのかについて簡単に説明します。
また血栓症のリスク(危険性)が高い人はどんな人か、血栓症を起こすとどんな症状が出るのかについてもまとめておきます。
低用量ピルの服用で血栓症のリスクが高まる理由
低用量ピルを飲むと血栓症リスクが高くなる理由は、血栓を作る働きとそれを邪魔する働きのバランスが崩れるからです。
低用量ピルを内服することにより、血栓を作るのに関係する物質(凝固因子;ぎょうこいんし)のいくつかが増えます。それと同時に、血栓ができるのを邪魔する物質(凝固抑制因子)のいくつかが減ります。これにより、低用量ピルを飲んでいる間、体の中は常に血栓ができやすい状態になっているのです。
血栓症のリスクが高い人
明らかに血栓症を起こすリスクが高い人がいます。下記に当てはまる方は、大規模研究で血栓症のリスクが高いことがわかっており、低用量ピルの内服にあたっては、他の持病なども含めて慎重に検討する必要があります。
- 肥満:肥満は、ピルを飲んでいなくても血栓症のリスクが高いです。BMIが20〜24.9の人がピルを飲んだ場合に血栓症を起こすリスクを1とすると、BMI25〜29.9の人は2.4、BMI30以上の人は5.5と非常に高くなっています。
- 40歳以上:年齢とともに血栓症のリスクは上昇します。30〜34歳の人のリスクを1とすると、40〜44歳で1.57、45歳以上だと2.09と高くなっています。
- タバコを吸っている:タバコを吸ったことがない人のリスクを1とすると、今はやめているがタバコを吸ったことがある人のリスクは1.63、今タバコを吸っている人のリスクは2.03まで上昇します。
- 血縁者に血栓症の人がいる:いない人と比べると、血栓症リスクは2.2倍高いです。
血栓症の初期症状
血栓症(深部静脈血栓症)の初期症状はふくらはぎの痛みやむくみです。血栓が肺まで到達し肺塞栓症を起こした場合は、激しい胸痛や胸の苦しさ、息切れなどの症状が突然現れます。
これらの症状が出た場合は、すぐに処方された医師にご相談ください。
低用量ピルの効果

低用量ピルは経口避妊薬として処方されることが多く、最も期待される効果は避妊効果です。正しく内服できていれば、妊娠回避率は99%以上です。ピルを内服することにより血液中の卵胞ホルモンと黄体ホルモンの量が増えると、脳が妊娠していると勘違いして排卵を止めてしまうのです。そのほか、子宮内膜が厚くなるのを防ぐ働きや、精子が膣から子宮に入りにくくする働きを持っていると言われています。
このほか、低用量ピルは生理不順のほか、PMSや生理痛・過多月経など月経困難症の症状を和らげる効果も持っています。通常は排卵や生理のたびに女性ホルモンのバランスが大きく変わり、PMSや月経困難症を引き起こします。低用量ピルによりホルモンのバランスが整うため、それらの症状が出にくくなるのです。
また、ホルモンバランスの乱れがなくなるため、ニキビや肌荒れが良くなる人もいます。
低用量ピルの服用方法

低用量ピルは1日1回、1錠を同じ時間に飲みます。これはどんなピルでも同じです。1シート21錠のタイプと28錠のタイプの違いは、休薬する期間が必要かどうかです。
1シート21錠のタイプには、ホルモンの含まれない偽薬(プラセボ)が含まれておりません。21錠を飲み切った後は、7日間内服をお休みしたのち、8日目に次のシートの錠剤を飲み始めます。お休み期間後の飲み忘れがないように気をつけましょう。
1シート28錠のタイプには、ホルモンの含まれない偽薬(プラセボ)が含まれています。28錠を飲み切った後は、翌日から次のシートの錠剤を飲み始めます。
副作用がつらい場合は病院へ相談を

低用量ピルの副作用がつらい場合は、処方された病院へ相談することをお勧めします。
低用量ピルを飲んでいる間に気をつけたい副作用は、吐き気や下痢です。吐いてしまったり下痢が続いたりすると、せっかく飲んだ低用量ピルが吸収される前に体の外に出てしまいます。
低用量ピルを飲んでから3時間以内に吐いたり下痢をしたりした場合は、すぐに1錠を追加して飲みましょう。翌日は通常の時間に1錠内服すれば問題ありません。
24時間以上吐いたり下痢が続いたりしている場合は、飲んだ薬がきちんと吸収されていないことが考えられます。この場合は十分な避妊効果が期待できないので、吐き気や下痢がおさまるまで低用量ピルの内服を中止します。吐き気や下痢が治まった後は、飲み忘れた場合と同じように内服を再開しましょう。
また、血栓症の危険を避けるため、長い時間同じ姿勢で座るのは避けましょう。旅行の際は適宜休憩を入れ、水分補給をしっかり行いましょう。
まとめ
- 低用量ピルの副作用は大きく「軽度(吐き気・頭痛・不正出血など)」と「重大(血栓症など)」に分かれる
- 服用開始後1〜3ヶ月で多くの軽い症状は落ち着き、重大な副作用(血栓症)は頻度こそ低いが早期発見が重要
- 乳がん・子宮頸がんとの関連は確定的ではないが、リスクが指摘されているので定期検診もおすすめ
- ピルの種類(世代)によって含まれるホルモンが異なるため、副作用の出方や傾向も変わる
- 自分の体質や悩みに合ったピルを選ぶことで快適に服用できる可能性が高まる
正しく服用すれば、低用量ピルは避妊はもちろん、生理痛やPMSなどを改善する強い味方です。不安な点や副作用の症状があれば、遠慮なく処方医へご相談ください。定期的な診察を受け、血液検査や子宮頸がん検診を受けながら安全に服用することで、より快適な生活を目指しましょう。
不安な点がありましたら、ぜひ当クリニックまでご相談ください。